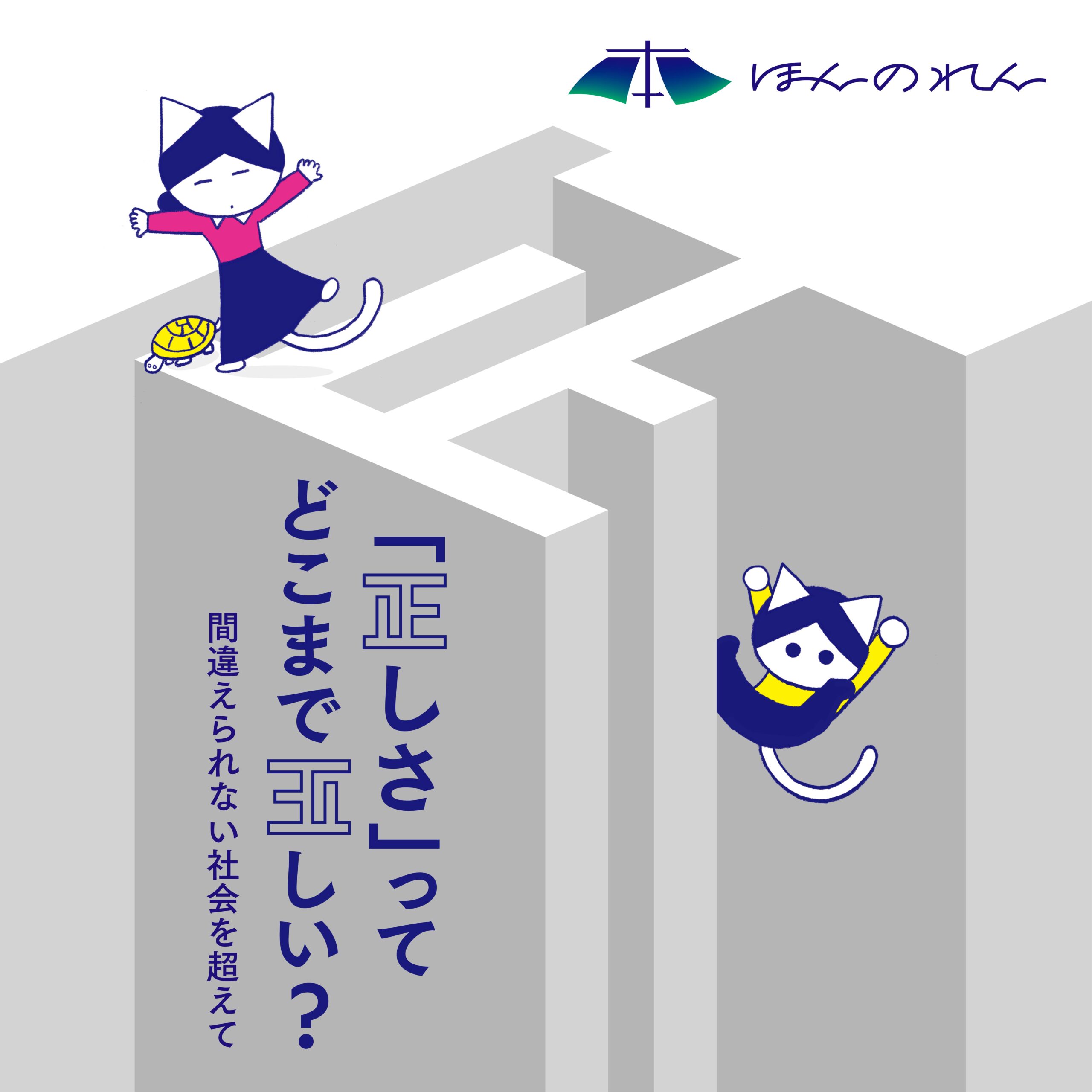-
[AIDA]ボードインタビュー:中村昇さん◆後編:「世界は編集行為で成り立っている」
- 2022/10/16(日)09:42
-


今年もハイパーエディティングプラットフォーム[AIDA]の季節がやってくる。「生命と文明のAIDA」を考えたSeason1から、Season2では「メディアと市場のAIDA」に向き合い、次なる2022年、10月開講のSeason3のテーマは「日本語としるしのAIDA」。あらたな「あいだ」に迫るべくプロジェクト・チームが始動した。新シーズンの到来とともに、過去シーズンのボードメンバーからの声に耳を傾けてみたい。
※内容は取材時のもの
前編はこちら
新型コロナウイルスの蔓延は世界の様相を一変させました。時々刻々と変わっていく状況に揺さぶられるように、わたしたちの価値観も大きな変更を迫られています。「これまで当たり前に存在していたモノやコトをあらためて見つめ直す機会として、現在のこの状況を捉え直してみるーー」。編集工学研究所は、現在、Hyper-Editing Platform [AIDA]を通じて各界の有識者と共に「編集的社会像」というコンセプトのもと、さまざまな角度から社会のあり方を考え直しています。
本稿では、『ホワイトヘッドの哲学』や『落語ー哲学』などの著書で知られる哲学者 中村昇が捉える世界および、世界との一体化に関する考えから「編集的社会像」のヒントを探ります。
中村昇(なかむら のぼる):1958年10月7日生まれ。日本の哲学研究者、中央大学教授。専門は英米哲学。ウィトゲンシュタイン、ホワイトヘッド、ベルクソンなど。1984年中央大学文学部仏文科卒。卒業論文指導教授は丸山圭三郎。1994年同大学院文学研究科哲学専攻博士課程満期退学。大学院では木田元に師事。2005年教授。2007年Center for Process Studies(アメリカ・カリフォルニア州、クレアモント大学)客員研究員。主な著書は『ホワイトヘッドの哲学』(講談社選書メチエ、2007)、『ベルクソン=時間と空間の哲学』(講談社選書メチエ、2014)、『ウィトゲンシュタイン『哲学探究』入門』(教育評論社、2014)など。
◆世界との関係:子どもの頃と現在の感触の違い

―― そのような世界の見方というか、<わたし>と世界との関係を中村さんが考え始めたのは、小さな頃からだったのですか。
中村 そうですね。小さい頃からわたしは、なぜ、われわれは、生きているのか、生きている意味とは何か、と考えていました。だいたいの人間は70〜80年というとても短い期間で死ぬじゃないですか。それなのに、生活のためにお金を稼いで、話題といえば、政治や経済や、どんな学校に行くとか、テレビやスポーツのことばかり。そんな大人たちを見て、ずいぶん能天気なものだと思っていたんです。
だから、大人たちは本当のことを絶対に隠しているはずだと本気で思っていました。きっといろんなことが分かる中学2年くらいになれば、自分の父親か、あるいは町の長老のような人が自分を、別室かお寺のようなところに呼んで、この世界の意味や、死んだ後のことを詳しく説明してくれると思っていたんです。でも、いつまで経っても誰も何も説明してくれない。
そこで、この秘密を解いてくれる大人はいないかと、小説とか評論とかを手当たり次第に毎日読んでいたのですが、高校生になって哲学者という連中がいることに気づきました。ベルクソンやショーペンハウアー、カミュなどという人と出会ったのです。特に、カミュの『シーシュポスの神話』には衝撃を受けました。「人間の生は意味もなく不条理なものなのだから、自殺するかどうかだけが人間の唯一の問題だ」と言うんです。その通りだと思いました。やっと自分に本当のことを教えてくれる人が現れたと思いました。
哲学者という人種は、自分が考えてきた問題にじっくり取り組んでいる。哲学者が書いた本を読めば、もしかしたら自分が抱えている悩みの解答にたどり着くかもしれないと思ったんです。
―― そこから中村さんが哲学者になるまでの間には何があったんですか?
中村 いろいろありました。高校の時、佐藤信が主催する「劇団黒テント」の演劇を見たんです。それがすごく面白かったので、芝居をやろうと思い、東京に出ました。そして東京でいろんな人たちとつきあっているうちに、暗黒舞踏に出会いました。麿赤兒(まろあかじ)の「大駱駝艦の天賦典式(だいらくだかんのてんぷてんしき)」にとても感動して、これだと思ったんです。その後、「暗黒舞踏」というジャンルを創設した土方巽(『病める舞姫』 – 千夜千冊 976夜)が主催する「アスベスト館」に入りました。1978〜80年頃で、当時19〜20歳くらいです。実は「遊学する土曜日」に行っていたのも、その頃なんです。松岡さんが語るホワイトヘッド、ウィトゲンシュタイン、量子力学、ロジェ・カイヨワ、稲垣足穂、アンドレ・ピエール・ド・マンディアルグなど、底の知れない驚くべき該博な知識に圧倒されました。20代は土方巽と松岡正剛という2人の深い影響のもとにすごしました。もちろん、いまもその影響圏内にいるといえるかもしれません。
土方巽さんはもう本当に変な人で、「これが、ようするに天才という人種なんだ」と思いました。「ものを食べるなんて興味ないです、ワインしか飲まないんです」とか言って、本当にそれを実行していたり、「奥歯からオペラが聞こえるように踊って」などと言ったり、いつも訳の分からないことを、ずっとしゃべり続けていました。東京の目黒に稽古場があったんですが、たとえば目黒通りの向こうから土方さんが歩いて来ると、もう空気が全く違う。只者じゃないんです。「私は只者ではありません!」という看板を出して歩いてくるんです。YouTubeにも映像が残っているんですが、大学の「舞台芸術論」という講義で学生にそれを見せたりすると、教室中が異様な引潮状態になります。
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ9xayQZKTX62wOT0NtSy2q-Mf03sOB5
しかし、2年ほど経って、これを一生続けるのは大変だと思って辞めました。大学に戻ってさて何をするかと考えた結果、哲学の大学院に行くことにしたんです。学部は、小林秀雄や澁澤龍彦の影響でなぜか仏文だったので、丸山圭三郎先生のゼミに入って卒論を出し、大学院からは哲学者の木田元先生(『偶然性と運命』 – 千夜千冊 1335夜)の研究室に行きました。要するに、堕落して舞踏を諦めた男が、小さい頃から気になっていた「問い」にもどって、哲学でもやろうかって感じでしたね。
◆<わたし>という他者

―― さまざまなプロセスを経て、いわば多世界に分岐していった先で、現在の哲学者である中村さんがおられるのですね。回顧的分岐によって過去のすべての可能性が畳み込まれている<わたし>という存在について、中村さんの考えを聞かせてください。
中村 <わたし>の内実は、4つの他者によって構成されていると思います。ランボーも、「わたしとは、一個の他者である」と言いましたが、わたしに言わせれば、「わたしとは、4つの他者である」ということになります。
1つ目は「身体という他者」。<わたし>は身体を持っており、これは自分自身のアイデンティティとして一番分かりやすいものです。でも身体って、とんでもなく<わたし>ではありません。なぜなら、身体は37兆個の細胞で成り立っていて、その膨大な数の細胞が、何をしているかなんて、<わたし>には、決してうかがい知れないからです。わたしの身体は、37兆個の細胞に、完全に乗っ取られているのです。その細胞だって、エネルギーの元であるミトコンドリアは、パラサイトなのです。わたしの身体を乗っ取っている37兆個の他者たちも、実は、乗っ取られていた。しかも、とんでもない長い期間。37兆個の他者たちが、われわれの身体なのです。とても、「わたしの身体」なんて、口が裂けても言えなくなります。
2つ目は「言語という他者」です。われわれは物を考える時には言語を使うわけですよね。でもそれだって自分で選んだわけではなくて、たまたま生まれた。九鬼周造のいう「離接的偶然」でしょうか。共同体のなかで大人たちが使っている言語をシャワーのように浴び、否応なくマスターさせられただけです。共同体の大人という他者たちによって、他者そのものである言語を問答無用で叩き込まれる、といった感じでしょうか。
かつ、その言語を使っていた大人だって、もちろん言語を自分で創ったわけではありません。ずっと昔から言語という他者的なものがその共同体を貫いているのです。言語は誰のものでもないし、かつ誰のものでもある。つまり、われわれの最も内奥に入り込んでいる「絶対的他者」なのです。そして言語でしかわれわれは思考できないので、そういう他者的なものでわれわれは意思疎通をしたり、していると思いこんだり、物を考えたり、考えていると思いこんだりしている。だからそもそもわれわれ自身の思考も他者に乗っ取られていて、自分で考えているわけではないと言えるでしょう。
3つ目は、「他人という他者」がいます。自分にとって、他人はとても分かりやすい他者です。しかし、この他者には絶対にタッチできません。たとえば、わたしはみなさん方のなかに入ることはできないし、もし仮に入れたとしても、わたしが入ればそれは<わたし>です。だから決してあなたにはなれない。自分と他人は原理的に「非対称」なのです。
そう考えると結局、<わたし>イコール世界ということになります。他人には、決して入ることはできないのですから、この世界は、<わたし>から出発して<わたし>で終わる。<わたし>を起点として世界を認識し、この<わたし>という視野のなかで世界は展開している
要するに、<わたし>というワンルームマンションのなかで、われわれは一生を過ごさないといけないということになります。この部屋から決して外へは行けません。その部屋の窓から外を見ると、絶対的な他者、あるいは他人が周りを取り囲んでいるというわけです。
最後に4つ目は、今まで3つの「他者」を指摘してきました。そういう「他者」を「他者」として指摘している<わたし>って一体何だ、ということですね。「他者」ではないこちら側ですね。つまり、いままで<わたし>と言っていたものは、一体何だということです。認識する主体(<わたし>)は、その主体そのものを認識することはできません。眼球で眼球を見ることはできないように、<わたし>が<わたし>をチェックすることはできないのです。チェックできたとしても、そのチェックしていた<わたし>を、またべつの<わたし>がチェックしなきゃいけないので、無限に後退していく。結局、認識している最中の<わたし>そのものは、絶対につかまえられない。そのつかまえることのできない<わたし>が、もっとも他者だといえるでしょう。何といっても、構造上、決して手つかずのままにならざるを得ないからです。いわば背後は背後のままなのです。振り返ると、そこには正面が現れるからです。背後は、原理的に背後のままなのです。この最後の他者(<わたし>)は、この「背後」と同じあり方をしているのです。
このように考えてくると、分かりやすい3つの他者が存在していて、さらにその3つの他者を他者だと認定していた<わたし>そのものが、最後に出てきた最も「底知れない」他者だったと分かります。<わたし>は、絶対に取り付く島のない「他者」であり、その後ろ姿さえ確かめることはできません。
◆「『絶対現在』が生成消滅しているだけ」の世界観

―― <わたし>や意志という概念の議論から派生して、言葉の機能や限界というところにまで話が進んでしまいました。ふだんビジネスの現場や日常生活で当たり前に使っている「わたしはこう思う」というような言葉も、一歩踏み込んで考えれば途端にあやふやなものになっていくことがみえてきたかと思います。それらを踏まえた上で、わたしたちが生きる世界としての編集的社会像を描くとしたら、中村さんはどう考えますか。
中村 <わたし>という<謎>の中心で、創造活動がなされていると考えてみたいのです。これからの人生で、この問題に正面から取り組みたいと思っています。つまり、この世界は瞬間創造的なあり方をしているのではないかと思うのです。「瞬間創造説」というのは昔からあり、デカルトやレヴィナス、西田幾多郎の哲学にもそういった側面があります。あるいは、仏教の刹那滅もまさにその通りでしょう。
先ほどの4つの他者のうちの4番目で、<わたし>そのものが実は他者だった、と言いました。<わたし>は自分を絶対にチェックすることはできない。一方でわれわれの眼前には、さまざまな物質が存在している。その物質は運動をし、世界は流動している。そして、<いま・ここ>で、<わたし>という背後で瞬間創造が起こっているというわけです。われわれには、けっして確認できない世界の根源にある<わたし>という深淵では、恒常的に「スモールバン」(small bang)が繰り返されているのです。その創造の結果を事後構成的に、われわれは確認している。それが、眼の前で展開されている世界だということになります。そして、その世界は、われわれの記憶の産物だといえるでしょう。なぜなら、われわれの周りには、<いま・ここ・わたし>からは遅れた過去の世界(痕跡)しかないからです。決して知りえない背後で、スモールバンが恒常的に生起している。それを、われわれは、自身の記憶の場所で、事後構成的にチェックしているだけ。これが、われわれのあり方だと思います。われわれは常に、瞬間創造された後の世界(痕跡)を見つめるしかないんです。
これを踏まえて「編集的社会像」を考えると、「編集」というのはとても面白い概念になります。「編集」というのは、この事後構成的なあり方に多分に影響されるものだと思うからです。われわれは、「スモールバン」、つまり背後の創造活動には、関与できない。つねに、何かが生みだされていく。何が生み出されるかは、予想も想像もできない。ひたすら、「他者」である<わたし>からあふれ出てくるものを、じっと確かめるしかない。「思考」や「会話」を例にとってみましょう。われわれは、自分自身で何かを考えるなんてことはできない。そう錯覚しているだけです。思考の道具である「言語」は、他者であるし、思考していると思いこんでいる<わたし>は、最も未知の底知れない深淵なのですから。
だとすれば、われわれにできるのは、「待つ」ことだけでしょう。何かが到来するのを、過去の時点から待っているしかない。われわれに到来したもの、スモールバンで発生し、その破片が過去化されたものを記憶の地平で扱うしかないのではないでしょうか。いいアイデアは「浮かぶ」のです。どこからかやってきて、記憶の領野に「浮かんでいる」のです。それをアレンジすることしか、われわれにはできません。こうして、<わたし>は、今回も、いろいろな突飛なことをお話しましたが、これも単に「浮かんだ」だけであり、<わたし>という「他者」のスモールバンの結果なのです。会話でも、講義でも同じことだと思います。とにかく、言葉が背後から噴出してくる。それを確認することだけが、われわれにできることであり、それが「原初的編集」とでもいえる作業だと思います。つぎつぎと喋るだけ。それを、直後に編集していく。これが、私たちの「思考」であり、「言語活動」だと思います。
そう考えれば、われわれにとって重要なのは、「わたし」という概念を消すことだと思います。「わたし」は存在しない。存在しているかもしれないが、この世界には、絶対に登場しない。余計な源にすぎない。<オリジナル>というまがい物です。われわれが手にすることができるのは、背後からの贈り物だけなのです。「わたし」という概念や「わたし」という単語を失くしてしまえば、われわれの世界は、すべてが一挙に変化するはずです。もしそうできたなら、この世界は、誰のものでもなく、誰のものでもある「編集」だけが残るでしょう。
たとえば、私は大学で学生に哲学を教えている。すると、学生よりはほんの少しだけ知識があると言えるかもしれません。しかしそれらはすべて受け売りです。ウィトゲンシュタインやホワイトヘッドから学んでいます。つまり、オリジナルは、つねに背後にあります。でも、そのウィトゲンシュタインやホワイトヘッドだって誰かの受け売りなのです。つねに、どこでも、誰でも、受け売りなのです。この「受け売り」という概念も、さきほどの「スモールバン」(=<わたし>における創造)と、過去化された眼前の風景との関係で説明できるでしょう。そして、つねに、「スモールバン」は、背後に退き続けます。永遠に後退し続けるのです。
<わたし>そのものはオリジナルなものですが、でもわれわれは決してそれにタッチすることができない。常にわれわれはオリジナリティが起こった後の状態を確認するだけ。必ず前から、あるいは、背後から何かを引き継いできているだけの存在であり、結局、われわれがたしかめられる世界のなかでは、オリジナルなものはどこにも登場しません。
だとすれば、われわれの世界には事後構成的な編集行為しかないことになります。「編集的社会像」を考えるにあたっては、まず<わたし>という概念を消すなどのやり方で、この世界が編集行為だけで成り立っているということを感じてみるといいかもしれません。
「待つ」こと、アイデアや思考や言葉が、どこからかやってくることを、じっと待つこと。じっとしなくてもいいかもしれません。「じたばた」でも「四苦八苦」でも「七転八倒」でも「只管打坐」でも、何でもいい。われわれが自分自身で何かをしているわけではなく、「創造」は、つねに背後で起こっていることを意識して、日々そのおこぼれを拾う体勢を整えていることが大切なのかもしれません。そういう「原初的編集行為」の集合体が、<わたし>にとっての「編集的社会像」であるとも言えるでしょう。 この世界が編集行為だけで成り立っているという認識に立てば、自ずと、編集の可能性も多様に開かれていくことと思います。
執筆:弥富文次
取材:橋本英人(編集工学研究所)
取材/撮影/編集:谷古宇浩司(編集工学研究所)
※2021年3月17日にnoteに公開した記事を転載