


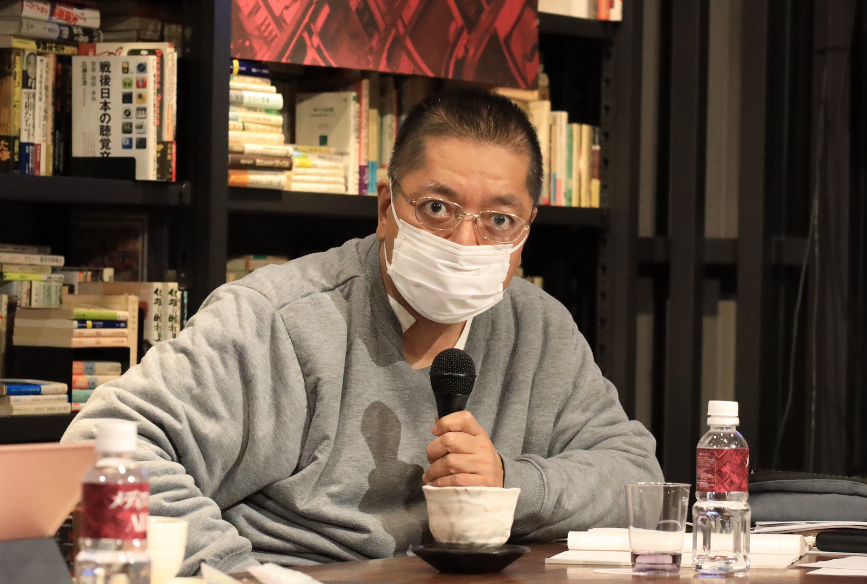
あのときはまだ爆撃音は聞こえなかった。一触即発のウクライナ情勢を世界中が見守っていた2022年2月12日、ハイパーエディティングプラットフォーム[AIDA]第5講が開催された。テーマは、多様なアメリカと監視資本主義。GAFAからメタヴァースまで、このインターネット時代に私たちはどう生きるべきか、軍靴の足音を遠くに聞きつつ議論が交わされた。プログラム終了後、AIDAボードメンバーである佐藤優氏に話を聞いた。
▽第5講速報記事:【AIDA Season2 第5講速報!】池田純一と武邑光裕に「監視資本主義とメタヴァースのAIDA」を学ぶ
(聞き手:梅澤奈央、取材日:2022/2/12)
■ ウクライナ危機に見る
「歴史なきナラティブ」の危険性
――松岡正剛座長は、現代の監視資本主義ではログがすべて残るため、過去の言説も現在のものとして扱われる危うさがあるとおっしゃっていました。佐藤優さんはどこに問題意識をおもちでしょうか。
佐藤:「歴史なきナラティブ」が問題ですね。第5講では、歴史に関する議論をもうすこし深めたかったです。
――今回のゲスト講師・池田純一さんは、アメリカ人は「アタシのアメリカ」を語り「ナラティブ」という言葉をよく使うと教えてくださいました。「歴史なきナラティブ」というと、陰謀論のようなものを想像してしまうのですが……。
佐藤:いや、それだけではありません。アメリカのバイデン政権も似たようなことをしています。2月12日現在、アメリカはおかしな主張をしています。ロシア軍がウクライナ軍を偽装し、そこへの攻撃をウクライナ侵攻の口実にするという「偽旗作戦」を実行しているとの主張ですね。これは合理的に考えれば筋が通っていないことがわかります。
――というと?
佐藤:まず、この作戦は稚拙です。もし偽旗を掲げてウクライナを攻撃すれば、偽装したロシア軍は全滅させられるはず。そんなオペレーションをロシアの軍参謀総長が許すでしょうか。
また、ロシアのメディアも黙ってはいないはずです。ロシアは、独立系新聞の編集長ドミトリー・ムラートフ氏がノーベル平和賞を受賞したように、メディアの諜報活動も盛んです。もし仮に、プーチン政権がウクライナ軍を偽装して戦争を始めるという謀略を組んだということが露見したら、政権は倒れます。ロシア市民は正義感が強いですから。
――なるほど、理屈で推定すればおかしいですね。どうしてアメリカはそんなデタラメを主張するのでしょうか。
佐藤:アメリカはウクライナ問題については、ひとつにまとまっているんですね。だからアメリカをまとめるために、無意識にやっているんでしょう。彼らにはそのように見えているんです。
――バイデン政権に有利だと考えるから、そういう政策が出てくるということですか?
佐藤:というよりも、彼らにとってはそれが「正しい」と感じているのだと思います。意識的にデタラメやっているなら矯正もできますが、無意識に正しいと信じているので、変えるのは難しいですね。たとえていうなら、束縛系、ドメスティックバイオレンス系のパートナーのようなものですよ。
――認知が歪んでいるということですか。愛しているつもりで傷つけるというのは、自覚がないぶん厄介ですね。
佐藤:とはいえ、ロシアがやっていることは、言うまでもなくめちゃくちゃではあります。ウクライナがNATOに加盟するかどうかなどは、その国の主権事項であって他国が干渉するものではありませんから。
■ 世界のなかの日本
アメリカ、ロシアにどう向き合うか
――日本はどう振る舞ったらよいのでしょうか。
佐藤:うまく体をかわすしかありませんね。このままアメリカの主張どおりになれば、アフガニスタンの悲劇が繰り返されるでしょう。日本政府はその危険性をわかっているので、同盟国でありながら最大限距離をおいていますが。
――考えたくありませんが、もし戦争が起こったら日本はどうなりますか。
佐藤:日本はスタグフレーションに見舞われるでしょうね。ヨーロッパとアメリカがロシアに禁輸し、ロシアから日本への天然ガス輸出が止まるでしょう。すると日本のガス価格は約4倍になり、電気代も倍に。となると食べ物も値上がりしてインフレが起こります。いっぽうで、コロナ禍で収入は変わらない。インフレと不況の最悪の状態になりますね。
――アメリカのナラティブと、我々の生活が密接につながっているのですね。
佐藤:そう。アメリカが歴史なきナラティブをもつことによって、我々の生活が台無しになることに気づかないといけません。
――日本人の生活も、歴史的に見ればずいぶん変化しましたよね。
佐藤:そうそう、いま透析のため病院に通っているのですが、ドラマを見ているんですよ。1991年にヒットした「東京ラブストーリー」ってありますよね。あのドラマは2000年にリメイクしたんですが、見比べて驚きました。明らかに、登場人物たちが貧しくなっています。主人公が住んでいるアパート、持っている車、待ち合わせる場所などの差は歴然です。
――あぁ、想像できます。91年というと「ジュリアナ東京」がオープンしたときですよね。バブルの予熱のある時代と今とでは、登場人物たちの考え方もずいぶん違っていそうです。
佐藤:原田曜平さんが『寡欲都市TOKYO』という本を出しておられました。その本によると、いまは若者は起業したとしても、売上が月15万でいいと言ってしまうほど「がっつく」という発想がなく、キーワードは「居心地」だといいます。
――利益ではなく売上で15万……。気の合う仲間と、ちょっとおもしろいことができればいいという感覚ですね。そういえば「東京で成功してやる!」というギラギラした人は最近見ない気がします。
■ 私たちはどこへ逃げるか
目指すは「中世のリアリズム」
――いま30代の私もふくめ、このどうしようもない社会が嫌で、「居心地のいい場」へ逃げたいと思っている人も多いと感じます。かといって、佐藤さんが著作で論じておられたように、かつてアジールだった宗教も、いまはあまり受け皿にはなっていません。逃げ場としてメタヴァースが選ばれているケースも多いように見えますが。
佐藤:こんなにきつい世の中ですから、逃げたいのがあたりまえでしょう。逃げる場所を確保するのは大事ですが、必要なのはリアルで信頼できる人4、5人でしょうね。
――今日のディスカッションでも「中世のリアリズムに戻れ」と強調しておられましたね。バーチャル空間への逃走ではなく、目には見えないけれど確実に存在するものに立ち戻るべし、と。
佐藤:そうですね。ただ、問題意識の高い人たちは、なかなか周りにそういう仲間を見つけるのが難しい。
――ふつうに生活していると難しいですが、AIDAやイシス編集学校も、そういう仲間を見つける場として機能していますよね。
佐藤:そのとおりです。松岡正剛座長のまわりに、知的な話を求めてくる人が集まっていますから。この場を見つけることができた人ならば、職場以外のコミュニティがあるということは知っているはず。だから、AIDAでもイシス以外の場でも、市民サークルでも見つけられるはずだし、作っていく力もあると思います。
――人間関係を築いていく力というのは、大人世代だけでなく、これからの子どもたちにも必須スキルになりそうですね。
佐藤:そうですね、多様な人と付き合える力が生きる力になるでしょうね。子育ての終わった同世代を見ていると、官僚や企業のトップなった人ほど、子どもを自由にさせているように見えます。自分たちが偏差値に縛られて勉強して、あまりいいことがなかったと感じているのではないでしょうかね。多様な人がいる場に子どもをおいて、さまざまな経験をさせる人が多いようです。
――「エンパシー」というスキルに光を当てたブレディみかこさんの著書『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』が思い出されます。これからの時代、多様な人たちと折り合いをつける力が必須スキルになりそうですね。
佐藤:あとは、本を読むことです。レーニンは困ったことがあると「マルクスに相談する」と言って、マルクスの本を読んでいたといいます。書籍を通じて、過去の人たちと対話していけばいいですね。
――歴史を学び、目の前の人と対話し、先人からも知恵を借りる。中世のリアリズムに戻りつつある現在、この地道な作業がいっそう力をもちますね。東京豪徳寺の本楼で、企業の枠を超えて多くの人達が膝詰めで将来を考えるAIDAの存在意義がさらに高まっていきそうです。
▼ハイパーエディティングプラットフォーム AIDA(座長松岡正剛)についてはこちらから
◎ついにオープン!オフィシャルウェブサイト:https://www.eel.co.jp/aida/
【プロフィール】
佐藤 優 さとう まさる
作家・元外務省主任分析官
1960年、東京都生まれ。同志社大学大学院神学研究科修了後、外務省入省。在英大使館、在露大使館などを経て、外務本省国際情報局分析第一課に勤務。本省国際情報局分析第一課主任分析官として、対露外交の最前線で活躍。2002年背任と偽計業務妨害罪容疑で東京地検特捜部に逮捕され、512日間勾留される。2009年最高裁で上告棄却、有罪が確定し外務省を失職。同年、自らの逮捕の経緯と国策捜査の裏側を綴った『国家の罠―外務省のラスプーチンと呼ばれて』で毎日出版文化賞特別賞を受賞。以後、文筆家として精力的に執筆を続けている。
写真:後藤由加里
梅澤奈央
編集的先達:平松洋子。ライティングよし、コミュニケーションよし、そして勇み足気味の突破力よし。イシスでも一二を争う負けん気の強さとしつこさで、講座のプロセスをメディア化するという開校以来20年手つかずだった難行を果たす。校長松岡正剛に「イシス初のジャーナリスト」と評された。
イシス編集学校メルマガ「編集ウメ子」配信中。
「知のコロシアム」とささやかれる、Hyper-Editing Platform[AIDA]。半年のあいだ、多彩なゲストやボードメンバーとともに知を深め、自己変容していくプログラムです。座衆と呼ばれる受講生は「常識がひっく […]
【リスキリングなら】勉強の仕方を学べるイシス編集学校!4/18(木)オンライン説明会あります。
大人になってから、もう一度学びなおしたくなる――。リスキリングやリカレント教育という言葉があたりまえになったいま、社会人になって大学や大学院に興味が向き始めた人も多いでしょう。 でも、そのときに悩むのが「何を」学ぶか、で […]
【イシスの推しメン26人目】ジュエリーデザイナー小野泰秀が、松岡正剛の佇まいに惹かれたワケとは
『デザイン知』。千夜千冊エディション2冊目にして、「デザイン」に関心のある者の心を鷲掴みにしていった1冊だ。ジュエリーデザイナーの小野泰秀さんは、松岡正剛による『デザイン知』の衝撃波をうけ、イシス編集学校へ入門。 なぜ、 […]
松岡正剛は、一世紀にひとりの天才だ。――佐藤優 多士済々の異才・哲人・哲人とともに対話し、思索を深める場。それが、Hyper-Editing Platform[AIDA]です。公式ホームページでは、ボードメ […]
【こまつ座への招待状】東京裁判を扱った公演『夢の泪』 井上ひさし生誕90年記念第1弾 4/6開幕
わたしたち日本人は、 どうしてこうも心楽しまない日々を送っているのでしょうか。 どうしてこうもどことなく不安な毎日を過ごしているのでしょうか。 日本国は、わたしたち国民が自らの手で そのあり方を創ってくこと […]
