私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。




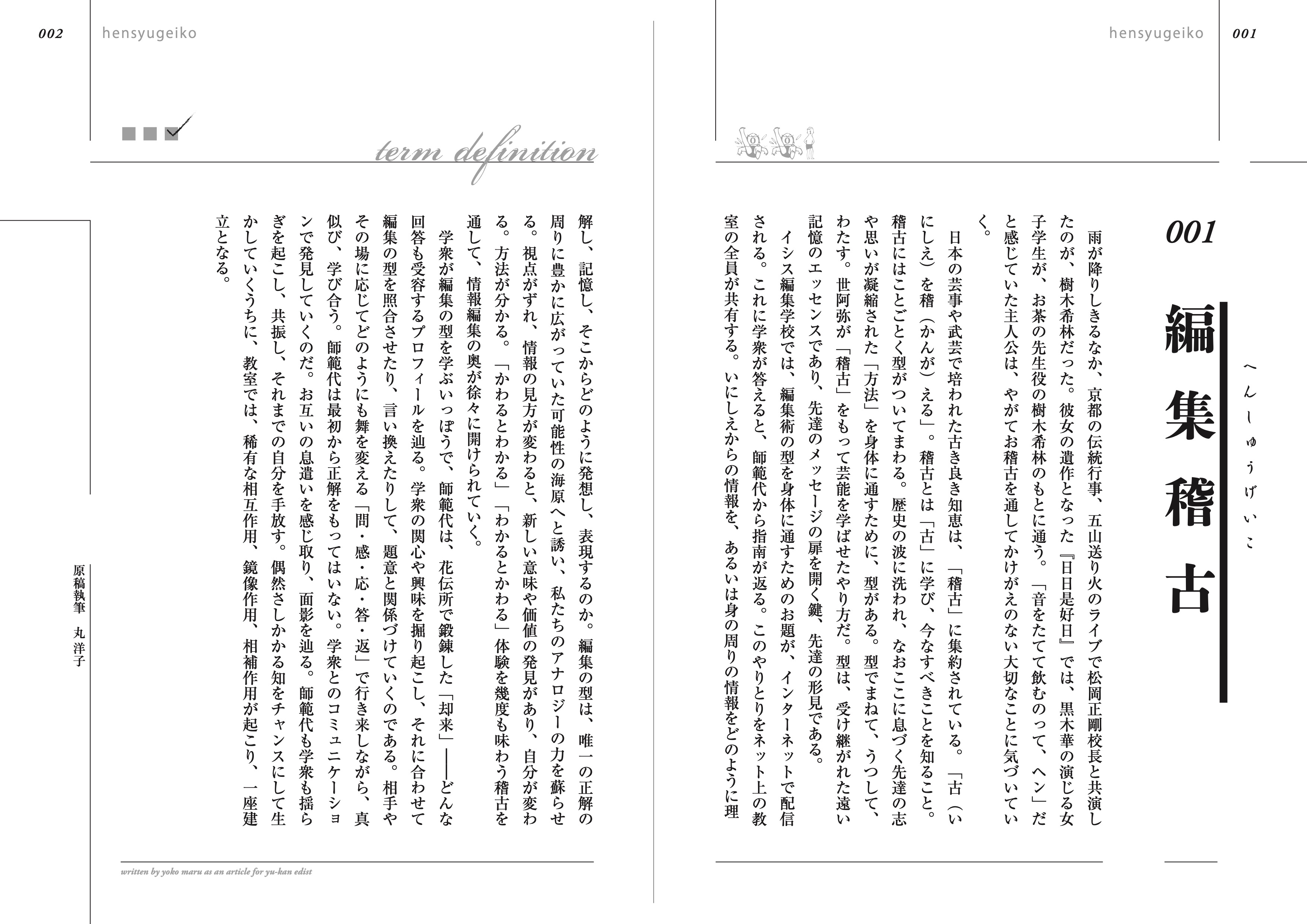
雨が降りしきるなか、京都の伝統行事、五山送り火のライブで松岡正剛校長と共演したのが、樹木希林だった。彼女の遺作となった『日日是好日』では、黒木華の演じる女子学生が、お茶の先生役の樹木希林のもとに通う。「音をたてて飲むのって、ヘン」だと感じていた主人公は、やがてお稽古を通してかけがえのない大切なことに気づいていく。
日本の芸事や武芸で培われた古き良き知恵は、「稽古」に集約されている。「古(いにしえ)を稽(かんが)える」。稽古とは「古」に学び、今なすべきことを知ること。稽古にはことごとく型がついてまわる。歴史の波に洗われ、なおここに息づく先達の志や思いが凝縮された「方法」を身体に通すために、型がある。型でまねて、うつして、わたす。世阿弥が「稽古」をもって芸能を学ばせたやり方だ。型は、受け継がれた記憶のエッセンスであり、先達のメッセージの扉を開く鍵、先達の形見である。
イシス編集学校では、編集術の型を身体に通すためのお題が、インターネットで配信される。これに学衆が答えると、師範代から指南が返る。このやりとりをネット上の教室の全員が共有する。
いにしえからの情報を、あるいは身の周りの情報をどのように理解し、記憶し、そこからどのように発想し、表現するのか。編集の型は、唯一の正解の周りに豊かに広がっていた可能性の海原へと誘い、私たちのアナロジーの力を蘇らせる。視点がずれ、情報の見方が変わると、新しい意味や価値の発見があり、自分が変わる。方法が分かる。「かわるとわかる」「わかるとかわる」体験を幾度も味わう稽古を通して、情報編集の奥が徐々に開けられていく。
学衆が編集の型を学ぶいっぽうで、師範代は、花伝所で鍛錬した「却来」――どんな回答も受容するプロフィールを辿る。学衆の関心や興味を掘り起こし、それに合わせて編集の型を照合させたり、言い換えたりして、題意と関係づけていくのである。相手やその場に応じてどのようにも舞を変える「問・感・応・答・返」で行き来しながら、真似び、学び合う。師範代は最初から正解をもってはいない。学衆とのコミュニケーションで発見していくのだ。お互いの息遣いを感じ取り、面影を辿る。師範代も学衆も揺らぎを起こし、共振し、それまでの自分を手放す。偶然さしかかる知をチャンスにして生かしていくうちに、教室では、稀有な相互作用、鏡像作用、相補作用が起こり、一座建立となる。

丸洋子
編集的先達:ゲオルク・ジンメル。鳥たちの水浴びの音で目覚める。午後にはお庭で英国紅茶と手焼きのクッキー。その品の良さから、誰もが丸さんの子どもになりたいという憧れの存在。主婦のかたわら、翻訳も手がける。
八田英子律師が亭主となり、隔月に催される「本楼共茶会」(ほんろうともちゃかい)。編集学校の未入門者を同伴して、編集術の面白さを心ゆくまで共に味わうことができるイシスのサロンだ。毎回、律師は『見立て日本』(松岡正剛著、角川 […]
陸奥の真野の草原遠けども面影にして見ゆといふものを 柩のようなガラスケースが、広々とした明るい室内に点在している。しゃがんで入れ物の中を覗くと、幼い子どもの足形を焼成した、手のひらに載るほどの縄文時代の遺物 […]
公園の池に浮かぶ蓮の蕾の先端が薄紅色に染まり、ふっくらと丸みを帯びている。その姿は咲く日へ向けて、何かを一心に祈っているようにも見える。 先日、大和や河内や近江から集めた蓮の糸で編まれたという曼陀羅を「法然と極楽浄土展」 […]
千夜千冊『グノーシス 異端と近代』(1846夜)には「欠けた世界を、別様に仕立てる方法の謎」という心惹かれる帯がついている。中を開くと、グノーシスを簡潔に言い表す次の一文が現われる。 グノーシスとは「原理的 […]
木漏れ日の揺らめく中を静かに踊る人影がある。虚空へと手を伸ばすその人は、目に見えない何かに促されているようにも見える。踊り終わると、公園のベンチに座る一人の男とふと目が合い、かすかに頷きあう。踊っていた人の姿は、その男に […]






コメント
1~3件/3件
2025-07-03

私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。
2025-07-02

連想をひろげて、こちらのキャビアはどうだろう?その名も『フィンガーライム』という柑橘。別名『キャ
ビアライム』ともいう。詰まっているのは見立てだけじゃない。キャビアのようなさじょう(果肉のつぶつぶ)もだ。外皮を指でぐっと押すと、にょろにょろと面白いように出てくる。
山椒と見紛うほどの芳香に驚く。スパークリングに浮かべると、まるで宇宙に散った綺羅星のよう。
2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。
写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。