草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。
「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。




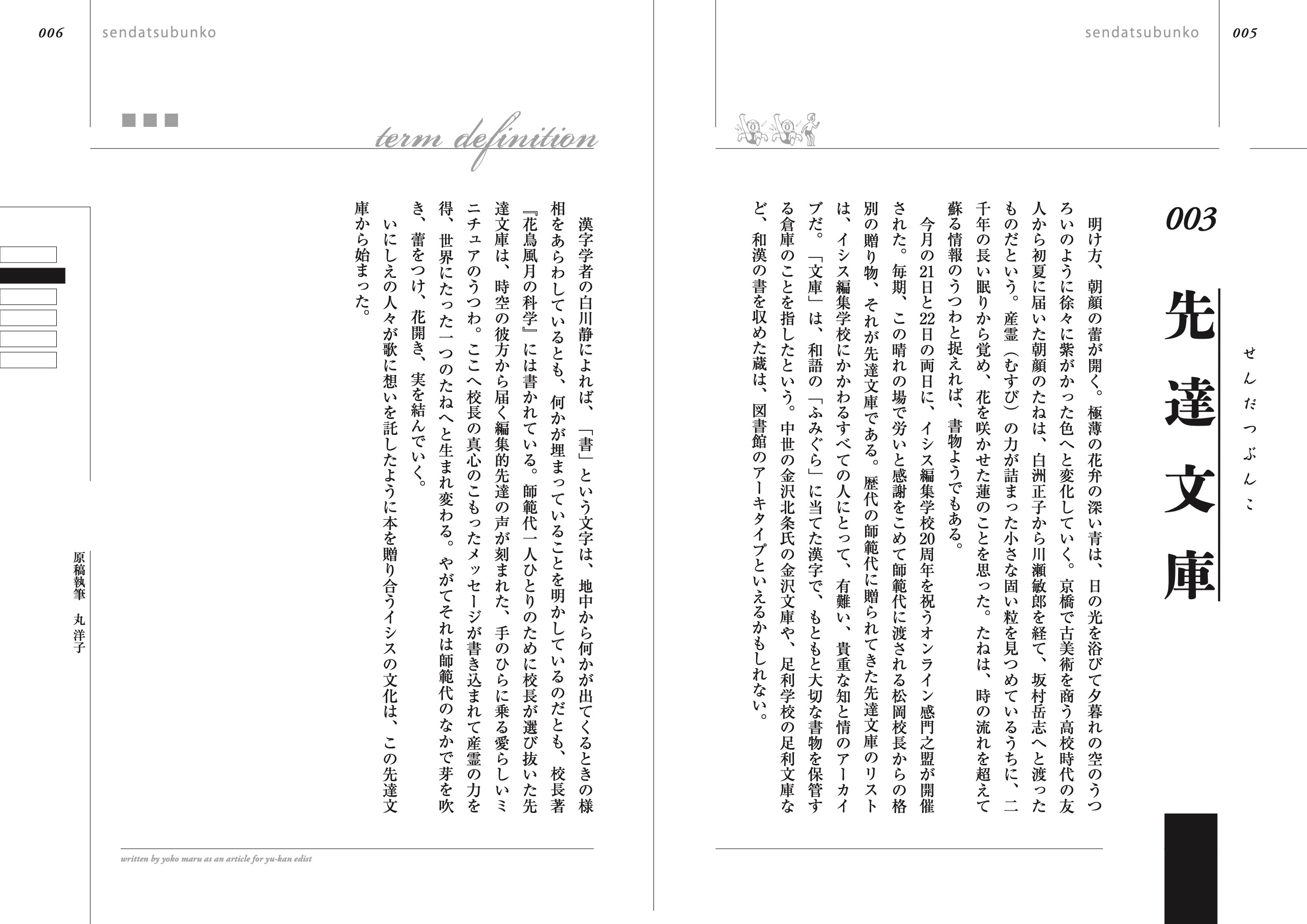
明け方、朝顔の蕾が開く。極薄の花弁の深い青は、日の光を浴びて夕暮れの空のうつろいのように徐々に紫がかった色へと変化していく。京橋で古美術を商う高校時代の友人から初夏に届いた朝顔のたねは、白洲正子から川瀬敏郎を経て、坂村岳志へと渡ったものだという。産霊(むすび)の力が詰まった小さな固い粒を見つめているうちに、二千年の長い眠りから覚め、花を咲かせた蓮のことを思った。たねは、時の流れを超えて蘇る情報のうつわと捉えれば、書物のようでもある。
今月の21日と22日の両日に、イシス編集学校20周年を祝うオンライン感門之盟が開催された。毎期、この晴れの場で労いと感謝をこめて師範代に渡される松岡校長からの格別の贈り物、それが先達文庫である。歴代の師範代に贈られてきた先達文庫のリストは、イシス編集学校にかかわるすべての人にとって、有難い、貴重な知と情のアーカイブだ。「文庫」は、和語の「ふみぐら」に当てた漢字で、もともと大切な書物を保管する倉庫のことを指したという。中世の金沢北条氏の金沢文庫や、足利学校の足利文庫など、和漢の書を収めた蔵は、図書館のアーキタイプといえるかもしれない。
漢字学者の白川静によれば、「書」という文字は、地中から何かが出てくるときの様相をあらわしているとも、何かが埋まっていることを明かしているのだとも、校長著『花鳥風月の科学』には書かれている。師範代一人ひとりのために校長が選び抜いた先達文庫は、時空の彼方から届く編集的先達の声が刻まれた、手のひらに乗る愛らしいミニチュアのうつわ。ここへ校長の真心のこもったメッセージが書き込まれて産霊の力を得、世界にたった一つのたねへと生まれ変わる。やがてそれは師範代のなかで芽を吹き、蕾をつけ、花開き、実を結んでいく。
いにしえの人々が歌に想いを託したように本を贈り合うイシスの文化は、この先達文庫から始まった。
丸洋子
編集的先達:ゲオルク・ジンメル。鳥たちの水浴びの音で目覚める。午後にはお庭で英国紅茶と手焼きのクッキー。その品の良さから、誰もが丸さんの子どもになりたいという憧れの存在。主婦のかたわら、翻訳も手がける。
「この場所、けっこうわかりにくいかもしれない」と書かれた看板を手にした可愛らしい男の子のイラストが、展覧会場の入り口に置かれている。眉根を寄せて地図を見ているその男の子を通り過ぎ、中へ進むと「あなたをずっとまっていたのか […]
八田英子律師が亭主となり、隔月に催される「本楼共茶会」(ほんろうともちゃかい)。編集学校の未入門者を同伴して、編集術の面白さを心ゆくまで共に味わうことができるイシスのサロンだ。毎回、律師は『見立て日本』(松岡正剛著、角川 […]
陸奥の真野の草原遠けども面影にして見ゆといふものを 柩のようなガラスケースが、広々とした明るい室内に点在している。しゃがんで入れ物の中を覗くと、幼い子どもの足形を焼成した、手のひらに載るほどの縄文時代の遺物 […]
公園の池に浮かぶ蓮の蕾の先端が薄紅色に染まり、ふっくらと丸みを帯びている。その姿は咲く日へ向けて、何かを一心に祈っているようにも見える。 先日、大和や河内や近江から集めた蓮の糸で編まれたという曼陀羅を「法然と極楽浄土展」 […]
千夜千冊『グノーシス 異端と近代』(1846夜)には「欠けた世界を、別様に仕立てる方法の謎」という心惹かれる帯がついている。中を開くと、グノーシスを簡潔に言い表す次の一文が現われる。 グノーシスとは「原理的 […]












コメント
1~3件/3件
2025-07-15

草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。
「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。
2025-07-13

『野望の王国』原作:雁屋哲、作画:由起賢二
セカイ系が猖獗を極める以前、世界征服とはこういうものだった!
目標は自らが世界最高の権力者となり、理想の王国を築くこと。ただそれだけ。あとはただひたすら死闘に次ぐ死闘!そして足掛け六年、全28巻費やして達成したのは、ようやく一地方都市の制圧だけだった。世界征服までの道のりはあまりにも長い!
2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。
配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。
昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。