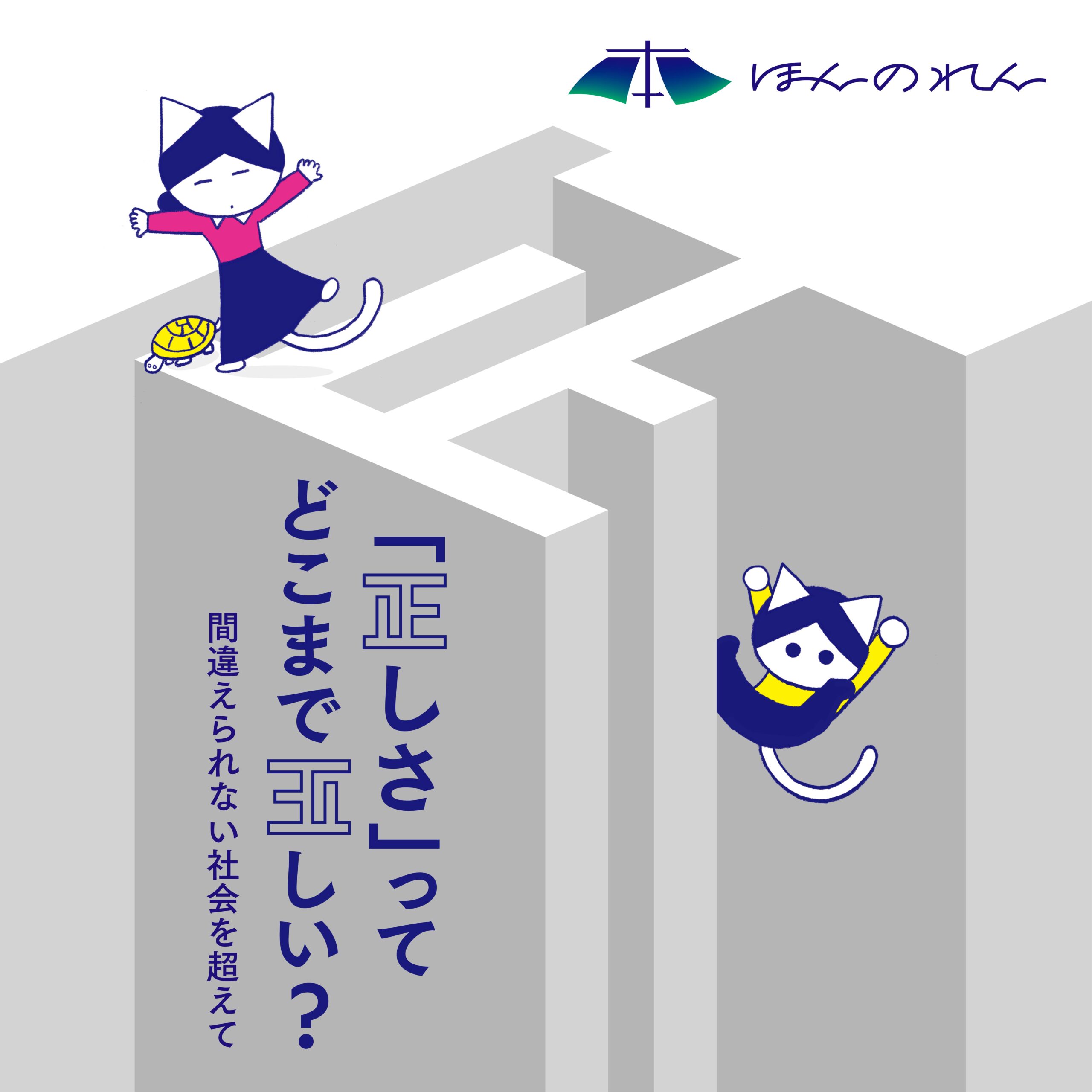-
【三冊筋プレス】数寄も見立てもなかりけり(小路千広)
- 2021/05/06(木)10:01
-


漢文の授業はチンプンカンプン。返り点なるものに翻弄されてどう読めばよいのかわからない。教科書を読み上げる教師の声だけが頭の中をむなしく通り過ぎていき、退屈で憂鬱で夢うつつな時間でしかなかった。心の底では一生お付き合いすることもないと思っていたけれど、この本のおかげでカマエが変わった。漢文の苦手な私にも読める書き下し文、しかも極上の解説つきというから読まない手はない。日本の古典と現代文のあいだに分け入ってみたい。
遊戯と真面目の端境に歌う
平安末期の宮廷歌人の家に生まれ、『千載集』の撰者として知られる藤原俊成を父にもつ藤原定家は、数え19歳から74歳まで半世紀以上にわたり漢文で日記を綴った。のちに『明月記』と呼ばれるこの膨大で難解な日記を読み解いてエッセイ風に綴ったのが、堀田善衛著『定家明月記私抄』である。
文筆家である堀田は、職業歌人であった定家に自分を重ね、当時の時代背景や独自の歌論をまじえながら明月記を繙いていく。大家族を養うための家計のやりくり、上司の命令に翻弄される官僚仕事のぐち、家業を守るための処世術に加え、病弱で頑固だったことなど。「ときとしてはその癇癪の高さがかえって当方の哄笑をさそったりもし、その哄笑の間に、苦虫を噛みつぶしたような定家氏の表情までが見えてきたりもするのである」と堀田が言うように、歌の大家としてのこれまでの人物像を覆し、世俗に生きた定家が見えてきて興味がつきない。宮仕えが嫌になり仮病をつかって休んだ記述には親しみさえわいてくる。
定家が歌人としての活躍期を迎えるのは四十代。後鳥羽上皇の勅命で編纂された『新古今集』の撰者に名をつらね、鎌倉幕府の若き征夷大将軍、源実朝と和歌を通じて親しくなった頃のことである。権力が貴族から武士へ移っていく端境期にあって、和歌もまた変容しつつあった。和歌はもともと和する歌。宮廷の歌会で公に交わし合う挨拶のようなものであり、コミュニケーションのツールであった。遊戯を好み秀でた歌人でもあった後鳥羽院は和歌に「景気」を求めたが、定家は「冷と静」を好み、自由に個人の心境を歌った。
定家の得意は和漢の古典を素養に寓意と象徴を尽くす技巧にある。
春の夜の夢の浮橋とだえして峰に別るゝ横雲の空
源氏物語の最終部「浮舟」をふまえて詠んだこの歌でも技巧派の本領を発揮している。堀田は定家の歌風を「官能と観念を交錯させ、匂い、光、音、色などのどれがどれと見分けがたいまでの、いわば混迷と幻覚性が朦朧模糊として、しかも艶やかな極小星雲を形成しているような境地にまで自分をもって行っている」と評し、新古今時代を「日本文学史上の高踏(パルナッス)の頂点」と賞讃する。
やがて承久の乱で敗れた後鳥羽院が宮廷を去ると、定家の風儀が、遊戯よりも真面目を是とする武家社会に受け入れられ、のちの侘茶へとつながっていく。日本の面影はここに大きな転換期を迎えたである。『定家明月記私抄』は移りゆく時世と文化を歴史的現在の目で伝える書物でもあった。
生命と霊性のあいだを探究する
端境は生命の領域にも存在する。植物と動物のあいだで変容する粘菌もそのひとつだ。アメリカ遊学時代にこの「動植物いずれともつかぬ奇態の生物」の魅力にとりつかれ、紀州田辺の森や庭で40年にわたり粘菌を観察し探究しつづけた南方熊楠。安藤礼二は『熊楠 生命と霊性』で、粘菌から曼陀羅を想起し、潜在意識へとアナロジカルな連想を展開する熊楠の思考をトレースしてみせた。
ちなみに熊楠は18歳から74歳で没するまで膨大な日記を書いた。大学や研究機関に属することなく、好きな生物学や民俗学に生涯をついやしたが、探究スタイルも独特だ。古今東西の文献を渉猟し、類例を発見する方法をとった。記録魔で古典に通じたところなど、どことなく定家と共通する部分が見えて面白い。熊楠は定家の明月記も読んでいたようだ。
安藤の熊楠論は、熊楠と前後してアメリカに渡り、禅の著作・普及を行った鈴木大拙の視点を採り入れることで定まった。ロンドンに移った熊楠と大拙のあいだをとりもったのは、1893年のシカゴ万国宗教会議に日本の仏教界を代表して出席した土宜法龍である。安藤は、熊楠がこのころに古生物学や神智学の書物を知ったことが、ダーウィンの進化論に疑問を抱き、粘菌や曼陀羅に興味をもつきっかけになったとみる。書簡のやりとりを通して議論するなかで、熊楠の曼陀羅と大拙の霊性が共振し、やがてそのあわいから近代日本思想の二つの系譜が誕生する。ひとつは柳田国男の民俗学と折口信夫の古代学、もうひとつは西田幾多郎の哲学である。
熊楠が遺した日記や書籍の研究が進みつつある。エコロジーへの関心が高まるいまこそ、熊楠の思想を深めるチャンスかもしれない。
健康と虚弱のハザマを生きる
大地震のような自然災害や感染症のパンデミックは世代間の断絶を露わにする。現在進行中の新型コロナウィルスへの対応も、高齢者と若者とのあいだにある意識格差を顕著にした例といえる。
ドイツに住み、作家として原発反対の声を上げる多和田葉子は、何かに違和感を覚えたときに自分の内から外に出る声(エクソフォニー)を言葉にし発信してきた。3.11後の2013年に福島を訪れ、翌年発表した小説『献灯使』の舞台は、大災厄に見舞われて鎖国状態にある日本。百歳を過ぎても健康な高齢者と虚弱で学校に通う体力もない子供が登場する。東京西域の仮設住宅に暮らす義郎と曾孫の無名だ。インターネットも車も外来語もない。あらゆることが江戸時代に逆戻りしたような暮らしは、エネルギーを浪費する現代社会への警鐘か。読み進むうちに本来のエコロジーライフを先取りしているのかもしれないと思えてくる。
小学生の無名は鳥のように細い脚をして歩行もままならない。食物の咀嚼に時間がかかり、オレンジジュースを常食としていても泣き言を言わず、自分を可哀そうだとも思わない。義郎はそんな曾孫を心配しながらも、弱体化する日本人が生き延びる可能性を見出すようになる。「もしかしたら無名たちは新しい文明を築いて残していってくれるかもしれない」。肉体と精神、進化と退化を問い直す見方は熊楠に類似するところがある。かくして15歳になった無名は「献灯使」に選ばれ、秘密裡にインドへ出発する。
多和田は日本の現状を世代間の極端な格差に誇張して描いた。ジョギングを「駆け落ち」と言いかえ、七十代後半を「若い老人」と呼ぶ独特の言葉遊びやレトリックにくすっとしながらも思い当たることはある。『献灯使』の世界観は、健康に呪縛された世代から不健康を自然な状態として受け入れる世代へ、意識転換が起きる端境期を暗示する。義郎が無名に託したミッションは変化を起こす嚆矢になること、すなわちトランスポーターなのである。
Info
──────────────────────────────
●参考千夜
∈0017夜『定家明月記私抄』堀田善衞
∈1624夜『南方熊楠全集』南方熊楠
∈1736夜『献灯使』多和田葉子
●アイキャッチ画像
∈『定家明月記私抄』堀田善衛/ちくま学芸文庫
∈『熊楠 生命と霊性』安藤礼二/河出書房出版
∈『献灯使』多和田葉子/講談社文庫
●多読ジム Season05・冬
∈選本テーマ:日本する
∈スタジオNOTES(中原洋子冊師)
∈3冊の関係性(編集思考素):三間連結型
『定家明月記私抄』→『熊楠』→『献灯使』