連想をひろげて、こちらのキャビアはどうだろう?その名も『フィンガーライム』という柑橘。別名『キャ
ビアライム』ともいう。詰まっているのは見立てだけじゃない。キャビアのようなさじょう(果肉のつぶつぶ)もだ。外皮を指でぐっと押すと、にょろにょろと面白いように出てくる。
山椒と見紛うほどの芳香に驚く。スパークリングに浮かべると、まるで宇宙に散った綺羅星のよう。




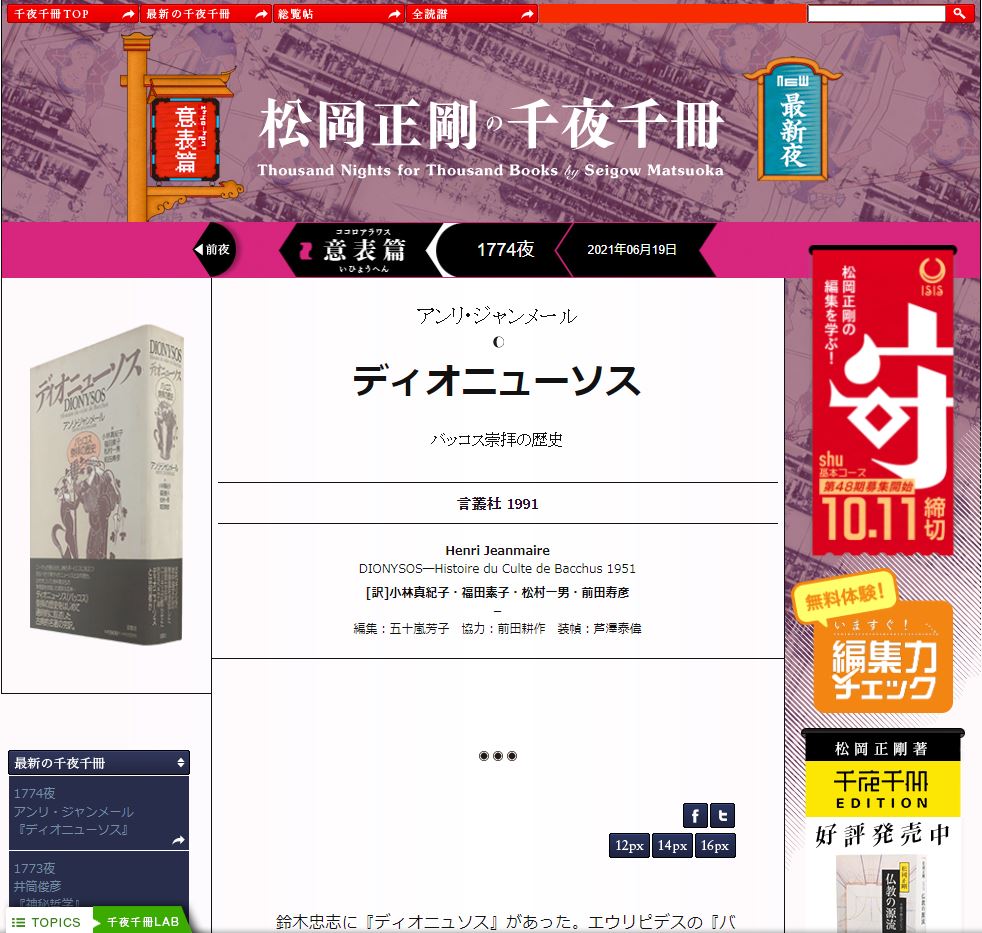
いや~、1774夜『ディオニューソス』アンリ・ジャンメールは読み応えがありました。これまでの『神秘主義』『占星術』『神秘哲学』と合わせて、四夜ひとつづきの一夜です(もちろん、さらに続くのかもしれませんが)。今回は、ギリシア神話のディオニュソス神を取り上げた一冊です。
★ディオニュソスとは
マニア(熱狂)やオルギア(騒擾)の神
一般的には、ディオニュソスは葡萄酒と酩酊と豊饒の神、非合理性と混沌の神として知られています。僕も存在くらいは知っていましたが、どんな神と聞かれたら、「えーと、たしかワインの神ですよね~」としか答えられませんでした。おそらく同様の方が多いのではないか、と思います。
1774夜によれば、ディオニュソスとは、マニア(熱狂)やオルギア(騒擾)の神です。「人々が酔いしれ、うっかりし、男女の境いをとびこえたくなるときの、そのように埒と不埒の両方をまたぐことになりかねない乱心の萌芽の集大成」としての神です。「ディオニュソスはこれ(騒擾)を大きくして騒然とさせることもできれば、それ(騒擾)を収めて収束することもできた」ので、騒乱の神であり、同時に救済の神でもあります。不思議な存在ですね。
松岡校長は、こうしたディオニュソス像を知って喜んでいらっしゃいます。「ぼくはこのようなジャンメールの解釈に快哉を叫んだものだった。そうなのである。ディオニュソスはまさに『別様の可能性』だけで想像された複相神だったのである」。
これは、今シーズンの多読ジム読衆にはおなじみ(でもない?)
ハドリアヌス帝に愛されて神格化されたアンティノウスの像ですが、
この像はディオニュソスの姿をしています。
★ヒトはそもそも秩序や物語や理性に
収まるような存在じゃない
ここから詳しい説明に突入するのは止めて、僕が1774夜を読んでどう感じたかをお話しします。僕は読みながら、「コロナ禍の日本」を想いました。だって、現在日本には、1774夜の道具立てが全部揃っているからです。
まず、秩序があります。緊急事態宣言、まん防、マスク、アルコール、検温、●●警察…。コロナ禍の日本では、秩序と取り締まりの力が平時よりも確実に強く働いています。僕は基本的にはおとなしくルールを守っていますが、周囲に人の少ない屋外を散歩するときはマスクをしないことが多いんですね、息苦しいから。そのくらいでも、たまに見知らぬ人から睨まれます。日本は本当に秩序を生真面目に守る人が多い国です。
一方で、マニア(熱狂)やオルギア(騒擾)とまではいかないかもしれませんが、夜に集まってお酒を飲んだりするくらいの人はけっこういますね。東京の歓楽街に行けば、いまも20時以降に開いている飲食店があり、ときどき見かけると例外なく混んでいます。店外にも客が溢れて、お酒を楽しんでいます。1774夜には、「ギリシア神話の各地の伝承の語りには、こうしたかなり多くの無名のマニア行動や奇妙なオルギア行為が大量に挟まれていた」とありましたが、コロナ禍の日本も同様です。
たぶん、世界はいつもそうなんです。秩序や物語や理性にはキレイに収まらない無数の存在がおり、無数の小さなマニア行動や奇妙なオルギア行為があったんですね。当たり前です。だって、ヒトはそもそも秩序や物語や理性に収まるような存在じゃないんですから。僕らは常に、秩序や物語や理性からはみ出しています。ただ、それらはあまり語られてこなかった。1774夜は、そういった語られてこなかったものの集大成がディオニュソスなのだ、と暴いた一夜です。さらにいえば、秩序や物語や理性から漏れたものが神秘主義やスピリチュアルにつながっているのだ、ということを書いた一夜です。
★アフターコロナは
新しい祭りを創り出すチャンスかも
ただ、有名人のマニアやオルギアとなると扱いが変わります。いま秩序を乱した芸能人や有名人は、主にネット上で次々にひどい目に遭っていますね。僕の目には、コロナ禍では全スキャンダルがいつもの何倍も強く叩かれているように見えます。とにかく、マニアやオルギアやルール違反がことごとく許せない日本、になっているようです。特にひどく叩かれた人は「贖罪の羊(スケープゴート)」といっていいでしょう。いまのところ、最大のスケープゴートは渡部さんか東出くんか木村花さんか。他にも続々と出てきてますね。彼らはまさに、「日本という集団を精神的に統合するための犠牲者」に見えます。個人的には、現代日本でそんな野蛮なことがあっていいのかな、とすら思うのですが。恐ろしい世の中です。
それから、ディオニューシア祭ではないけれど、やはり古代ギリシアで生まれた祭典「オリンピック」が始まりますね。祭りはマニアやオルギアの極みですが、今回はなんとも分が悪い。これだけ秩序を守らせる力が強い状況で、オリンピックがどこまで盛り上がるのか。祭りの機能をどこまで果たせるのか。ワクチン接種率が高くなれば楽しいオリンピックになるのかもしれませんが、やはり少々タイミングが悪いように見えます。
ただ、コロナ禍が収まったときには、むしろ何か大きな祭りがあったほうがいいんじゃないでしょうか。本当はみんながみんな、自らの心身に蓄積されたマニアやオルギアの種をどうにかしたいんですから。このままスケープゴートを増やすくらいなら、祭りでパーッと気分を晴らしたほうがずっとよいでしょう。もしかしたら、アフターコロナは新しい祭りを創り出すチャンス、なのかもしれません。
僕なりに現代日本を重ね合わせながら、1774夜を読んでみました。皆さんの一助になれば嬉しいです。
米川青馬
編集的先達:フランツ・カフカ。ふだんはライター。号は云亭(うんてい)。趣味は観劇。最近は劇場だけでなく 区民農園にも通う。好物は納豆とスイーツ。道産子なので雪の日に傘はささない。
♪♪♪今日の舞台♪♪♪ 踊り部 田中泯 「外は、良寛。」 田中泯さんの踊りには、「いまここの生」を感じました。松岡正剛さんの『外は、良寛。』(講談社文芸文庫)のフラジリティには撃たれ、杉本博司さんの設えに […]
庵主・田中優子が「アワセとムスビ」で歴史を展く【間庵/講1速報】
2022年7月24日、「間庵」が開座した。庵主は、江戸文化研究家であり、松岡の盟友でもある田中優子さんだ。間庵は田中庵主が中心となり、リアル参加者の「間衆」とともに松岡正剛座長の「方法日本」を解読、継承、実践し、編集工 […]
【AIDA】リアルが持っている代替不可能な感覚情報がAIDAで鮮明になった<武邑光裕さんインタビュー>
メディア美学者・武邑光裕さんは、1980年代よりメディア論を講じ、インターネットやVRの黎明期、現代のソーシャルメディアからAIにいたるまでデジタル社会環境を長く研究する専門家だ。ドイツ・ベルリンを中心としたヨーロッパ […]
【AIDA】AIDAでは抽象度の高い議論と身の回りの話が無理なくつながる<村井純さんインタビュ―>
村井純さんは「日本のインターネットの父」である。村井さんが慶應義塾大学/東京工業大学間でコンピュータをネットワークでつなげたのが、日本のインターネットの誕生と言われている。その後も、黎明期からインターネットの技術基盤づ […]
「学校教育ができないことばかり実現している学校ですね」田中優子先生のエール!【78感門】
皆さん、まことにおめでとうございます。今日は、法政大学総長時代に卒業式で着ていた着物でまいりました。 2日目の冒頭は、田中優子先生の挨拶で始まった。優子先生は守・破・離をコンプリートし、今回は物語講座1 […]






コメント
1~3件/3件
2025-07-02

連想をひろげて、こちらのキャビアはどうだろう?その名も『フィンガーライム』という柑橘。別名『キャ
ビアライム』ともいう。詰まっているのは見立てだけじゃない。キャビアのようなさじょう(果肉のつぶつぶ)もだ。外皮を指でぐっと押すと、にょろにょろと面白いように出てくる。
山椒と見紛うほどの芳香に驚く。スパークリングに浮かべると、まるで宇宙に散った綺羅星のよう。
2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。
写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。
2025-06-30

エディストの検索窓に「イモムシ」と打ってみたら、サムネイルにイモムシが登場しているこちらの記事に行き当たりました。
家庭菜園の野菜に引き寄せられてやって来る「マレビト」害虫たちとの攻防を、確かな観察眼で描いておられます。
せっかくなので登場しているイモムシたちの素性をご紹介しますと、アイキャッチ画像のサトイモにとまる「夜行列車」はセスジスズメ(スズメガ科)中齢幼虫、「少し枯れたナガイモの葉にそっくり」なのは、きっと、キイロスズメ(同科)の褐色型終齢幼虫です。
添付写真は、文中で目の敵にされているヨトウムシ(種名ヨトウガ(ヤガ科)の幼虫の俗称)ですが、エンドウ、ネギどころか、有毒のクンシラン(キョウチクトウ科)の分厚い葉をもりもり食べていて驚きました。なんと逞しいことでしょう。そして・・・ 何と可愛らしいことでしょう!
イモムシでもゴキブリでもヌスビトハギでもパンにはえた青カビでも何でもいいのですが、ヴィランなものたちのどれかに、一度、スマホレンズを向けてみてください。「この癪に触る生き物をなるべく魅力的に撮ってやろう」と企みながら。すると、不思議なことに、たちまち心の軸が傾き始めて、スキもキライも混沌としてしまいますよ。
エディスト・アーカイブは、未知のお宝が無限に眠る別銀河。ワードさばきひとつでお宝候補をプレゼンしてくれる検索窓は、エディスト界の「どこでもドア」的存在ですね。