私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。





江戸文化およびアジア研究の異例のエキスパートであり、和服姿がトレードマークの法政大学総長。松岡正剛校長と三十年以上の親交があり、イシス編集学校の[守]・[破]・[離]、さらに[遊]風韻講座を受講した学衆でもある田中優子さんに、2019年末、エディスト編集部が突撃インタビューを実施した。
受講の感想、大学教育、江戸の寺子屋、松岡正剛との出会い、文体論、そもそも学びとは何か、いよいよ20周年を迎えるイシス編集学校にとって、ひいては激動のグローバル社会をサバイバルする日本人にとって、切実ありったけのQをぶっちゃける。
―――はじめに、編集学校に入学しようと思ったきっかけを聞かせてください。どんなところに関心をお持ちになったんですか。
そもそも、大学で長い間、文章指導をしていたんですね。ですから、人の文章をどう導いていくか、その人が持っている文章力や個性を伸ばすためにはどうしたらいいかということを教師としてずいぶん考えてきました。
文章にはそれぞれ個性がありますから、同じ内容でも、同じ資料を使ってもかなり変わる。ぜんぜん違ってくる。それは全身から出てくるものだからですね。文章というのは、息づかいというか、リズムというか、きわめて個人的で、個性的なものだと思っています。
だから、「直す」という指導法はあまりよくありません。みんな同じ文章にするのではなく、それぞれが持っているものを伸ばしていった方がいい。そうなると、やっぱり一人ひとり指導しなくてはならない。イシス編集学校はそれをすでにやっています。しかも、一人の師範代が何人かの面倒をみながら、一人ひとりに教えている。これは寺子屋方式です。

田中優子先生にインタビューする金副編集長。
(法政大学総長室にて)
―――寺子屋方式ですか。寺子屋ってどんな学び舎だったんですか。
江戸時代の寺子屋には、現代の学校のように同じような子どもは集まっていません。レベルも違うし、年も違う。いろいろ違っている生徒たちを一緒にみながら、一人ひとり指導していきます。 イシスがこういう方式をもっているというのがまずはうらやましい。
というのも、大学で文章指導をするときは、その場で一人ひとりに指導はできません。一つのテーマを与えて書いてきたものを、家に持ち帰って添削します。これはものすごく大変な作業です。 でも、それはやらなければならないし、やれば確実に伸びるんです。そういうことを経験してきたので、これを超スピードで添削したり、あるいは添削までしなくてもアドバイスして、伸ばしていくイシスの指導法はどんなものなのだろうとまず指導の方法に関心をもったわけです。これが入学した一つ目の理由です。編集学校の師範代の「指南」のあり方に関心を持ちました。
―――なるほど、もう一つの理由というのは。
編集学校は決して文章指導だけの学校ではありませんね。発想法、思考の組み立て方、つまり編集方法を伝授する。ほとんどの大学の文章指導ではこれがないんです。良い文章が書ければいいんでしょみたいなことになってしまう。もしそこに方法の指導があるとしても、添削する教員の方法が伝わるという程度にすぎないんですね。
そうすると、文章はよくはなっているけど、それがいったいどういう理屈でそうなったのかが分からないまま卒業してしまう。一応書けるようにはなるけれど、これはまずいことだなと思っていました。私自身、実際に教えているというそのこと自体がどういうことだったのかを客観視しないままやっていた。大学の指導法が個人から個人へというやり方でいいのだろうかとずっと疑問に思ってきました。これが入学の理由の二つ目、「方法」への関心です。それから最後にもう一つ、それは「読書」です。
―――「指南」「方法」ときて、三つ目が「読書」ですね。
編集学校では、方法を手にするだけではなく、だんだん進むに従って大量の本を読むようになりますよね。学部長になり、総長になり、忙しくなってきて、どんどん読めなくなってきたんです。
電子書籍化して、とにかく移動中に読むようにしているんだけど、偏るんですね。依頼された原稿や書評や賞の審査や、その他総長として読まなければならないものもあって、そういうのは「仕事としての読書」ですね。他に読みたい本があっても、今やらなければならないもの以外読めなくなっている。それをなんとかしなければならない。つまり、広げなければならない。私はつねに認識を広げなければならないと思っています。
専門家、研究者としての専門家が陥りがちなのが「狭く深く」です。でも、本当は狭いと深くなんてならない。それは経験的に分かる。一生、一人の作家の研究しかしない専門家もいます。それは教師としては成り立つんだけど、ではその人の書くものが本当に人の心を打つのか、新しいものを開くのかというと、決してそんなことはない。やっぱり狭いと深くはならない。
逆に、自分はこの分野でと思いながらも、「これはこれに関係あるよね」と好奇心が飛び火して、回収するのが大変なくらいどんどん広がっていくという傾向が私にはあるんだけれども、そうした方がものが分かるということにだんだんと気がついてきた。全体像が見えてくるので、広げれば広げるほど深くなっていく。だから、読書時間が減って、自分が広がらない状態になっていくことが非常に大きな問題だなと思っていました。で、広げるためにどうすればいいのか。強制的に広げるなら世界読書の[離]だなと。これが三つ目の理由です。
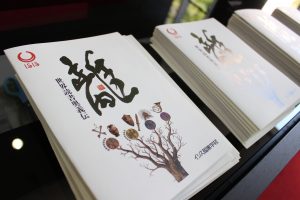
―――[守]を受講した時から[離]を受けようと考えていましたか。そもそも優子先生は、松岡校長も絶賛する独自のスタイルというか、編集方法を持っているのに、しかも超多忙なスケジュールを抱えながら、編集学校に入って[守]・[破]・[離]を受講したことがすごいなと思います。
まともな研究者なら、自分が全部わかっているとか、やり方を知っているなんて思っていません。そんなこと思っていたら変な人ですよ(笑)。最初の頃は時間がなくて、何度かつまずくこともありましたが、はじめから[離]まで行くつもりでした。多忙は、そうですね、意欲さえあればなんとかなります。
今やっておかないとできないかもしれないという危機感ですよね。時間がないからできないっていうのは、まあ、結局は言い訳です。ですから、それでやめておこうと言ってしまうと永遠にそうなるから、勢いでやってしまおうと(笑)。
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
基本コース [守] 申し込み受付中
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
つづく
金 宗 代 QUIM JONG DAE
編集的先達:宮崎滔天
最年少《典離》以来、幻のNARASIA3、近大DONDEN、多読ジム、KADOKAWAエディットタウンと数々のプロジェクトを牽引。先鋭的な編集センスをもつエディスト副編集長。
photo: yukari goto
佐藤優さんから緊急出題!!! 7/6公開◆イシス編集学校[守]特別講義「佐藤優の編集宣言」
佐藤優さんから緊急出題!!! 「佐藤優の編集宣言」参加者のために佐藤優さんから事前お題が出題されました(回答は必須ではありません)。回答フォームはこちらです→https://forms.gle/arp7R4psgbD […]
多読スペシャル第6弾「杉浦康平を読む」が締切直前です! 編集学校で「杉浦康平を読む」。こんな機会、めったにありません! 迷われている方はぜひお早めに。 ※花伝寄合と離想郷では冊師四人のお薦めメッセージも配信 […]
「脱編集」という方法 宇川直宏”番神”【ISIS co-missionハイライト】
2025年3月20日、ISIS co-missionミーティングが開催された。ISIS co-mission(2024年4月設立)はイシス編集学校のアドバイザリーボードであり、メンバーは田中優子学長(法政大学名誉教授、江 […]
【続報】多読スペシャル第6弾「杉浦康平を読む」3つの”チラ見せ”
募集開始(2025/5/13)のご案内を出すやいなや、「待ってました!」とばかりにたくさんの応募が寄せられた。と同時に、「どんなプログラムなのか」「もっと知りたい」というリクエストもぞくぞく届いている。 通常、<多読スペ […]
【6/20開催】鈴木寛、登壇!!! 東大生も学んだこれからの時代を読み通す方法【『情報の歴史21』を読む ISIS FESTA SP】
知の最前線で活躍するプロフェッショナルたちは、『情報の歴史21』をどう読んでいるのか?人類誕生から人工知能まで、人間観をゆさぶった認知革命の歴史を『情歴21』と共に駆け抜ける!ゲストは鈴木寛さんです! 「『 […]











コメント
1~3件/3件
2025-07-03

私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。
2025-07-02

連想をひろげて、こちらのキャビアはどうだろう?その名も『フィンガーライム』という柑橘。別名『キャ
ビアライム』ともいう。詰まっているのは見立てだけじゃない。キャビアのようなさじょう(果肉のつぶつぶ)もだ。外皮を指でぐっと押すと、にょろにょろと面白いように出てくる。
山椒と見紛うほどの芳香に驚く。スパークリングに浮かべると、まるで宇宙に散った綺羅星のよう。
2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。
写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。