草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。
「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。




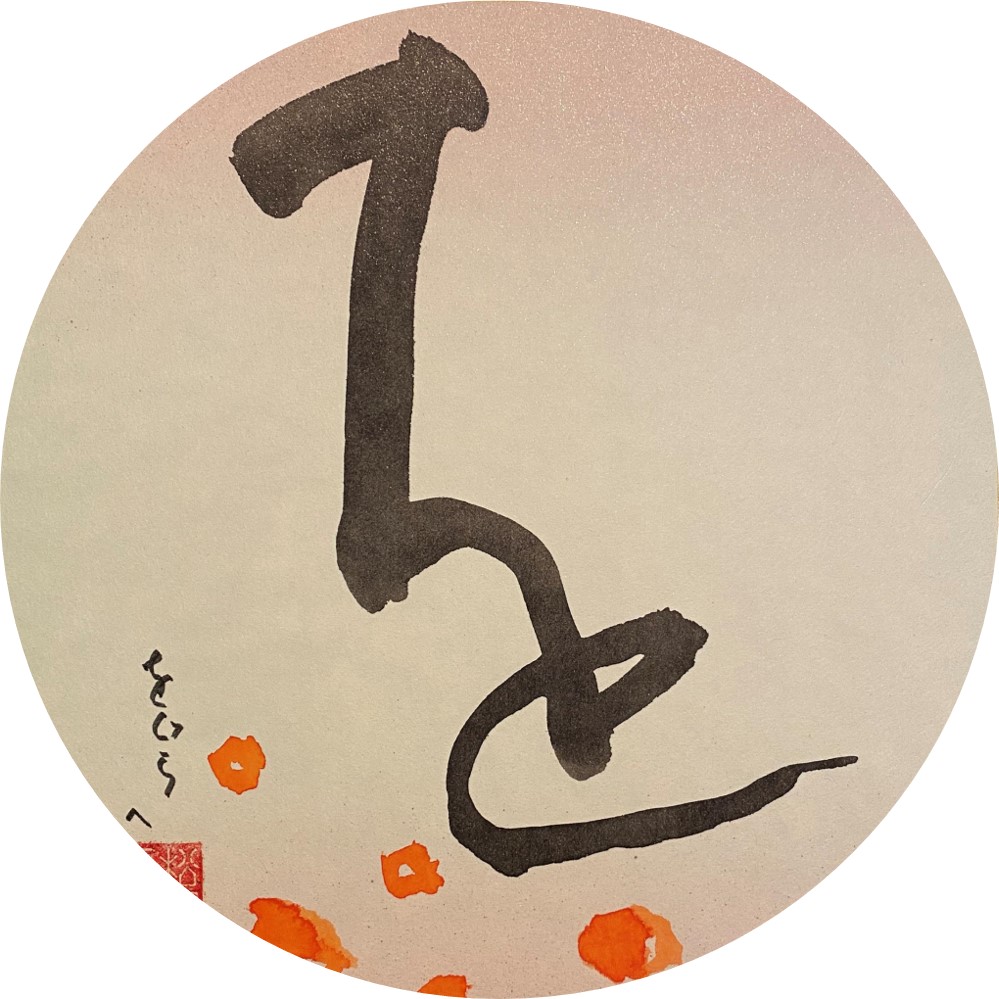
世界読書奥義伝 第14季[離]は、師走に入り、早くも第2週を終えました。苛烈な[離]は、離学衆にとまどいやためらいの暇さえ与えず、ひらめきとときめきを歓迎しながら一気に第3週を迎えようとしています。
「をぐら離」では、析匠、小倉加奈子の日常を通した離の姿をお届けしていきます。門外不出の文巻テキストをもとに進められていく離の稽古の様子を少しでも想像いただければと思います。
11月29日(日)
◆
ノーマンと僚友のデービッド・ラメルハートは、その学習行為の基本が、①蓄積(accretion)、②調整(tuning)、③再構造化(restructuring)の三つでできているとみなした。
──千夜千冊1564夜『エモーショナル・デザイン』
桂右筆が、「中身が形を決めていく」と指南で言っていた。これは図解も文章も同様である。校長の千夜ごとのモード文体も中身が形を決めていった結果であり、最初からモードありきなのではない。
稽古の進捗を見つつ、関連千夜にあたり、締切原稿やMEdit Labo用のイラストを描く。MEdit Laboでは、デザイナー穂積くんのセンスからたくさん学びたい。
蓄積→調整→再構造化。編集工学のプロテジェであり続ける毎日。
11月30日(月)
◆
言葉だって意味をとらえるための道具なのである。意味をとらえたあとは、言葉には用がなくなるはずなのだ。私は、そのように言葉を忘れることのできる相手を探して、ともに語りあいたいものだ。
──千夜千冊726夜『荘子』
荘子の「寓言、重言、卮言」は、生命・歴史・文化の3つの軸で現象を語る方法に思える。いつも言葉が追いつかないもどかしさを感じるが、図解したからといって、そのもどかしさは消えず。でもそのもどかしさこそが何かを企む原動力なのだ。
わたしも言葉を忘れられる相手ととことん語りたい。それは「夢」でも「擬」でもいいのだ。忘れられない人との面影編集でもある。
12月1日(火)
◆
「小を大とし、少を多とする」と言い、「難をその易に図り、大をその細に為す」と言っているのが、すばらしい。小こそが大であり、少こそが多なのである。そのうえで天下の難事はそれが易しいうちに手がけ、天下の大事に向かうときはそれを細かいところから取り組みなさいというのである。
──千夜千冊1278夜『老子』
早くも師走である。苛烈な稽古を横目に検査センターで骨髄像を診断する。鹿児島と札幌の血液疾患。わたしの手元に運ばれた眼下の細胞たちを観察しながら、南北それぞれ遠く離れた患者さんに想いを馳せる。
コロナウイルス流行が加速している。病理検査室では、クラスター騒動から1日100件前後のPCR検査が行われている。大赤字の病院の中、病理検査室のみコロナ景気が到来しているのは皮肉だ。
老子のフラジャイルな国家論を大いに参考にした病院経営、そして政策を。
12月2日(水)
◆
体調か、人間関係か、人生に倦いたのか。いや、そういうのじゃない。ひょっとすると、周囲がすべてネット環境になっていることと関連しているのかもしれない。あそこには刺激と欲望がめちゃくちゃに散乱していて、そんなことに冒されるはずがないと思っていたのに、いつのまにか集中力が擾乱されてしまったのかもしれない。
――千夜千冊1632夜『それでも、読書をやめない理由』
夜、松岡校長交えてのオンライン会議。会議の終盤、読書における集中力の分断と欠如が話題になった。LINEはためらいと突起がないと校長。話題の先端のみだけの交し合いによってすべてがばらばらになると香保総匠。わたしたちのリテラシー能力の何かが大きく損なわれているヤバさ。
微生物の共有がなされないコミュニケーションであることも問題かもしれない。密じゃなくとも空間を共有するとそこに集う人々は微生物込みの共同体となる。わたしたちは言葉や身ぶりだけではなく、微生物の交換を介してコミュニケーションをしているのだから。
微生物を介さなすぎる市場経済と文化システムの行き過ぎによって、コロナが到来したのだろうか。
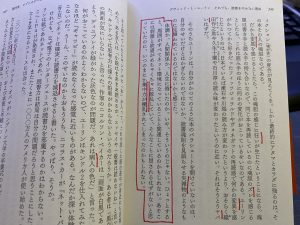
12月3日(木)
◆
しかし実は、レキシコグラファーの歴史ははるか昔のシュメール時代にさかのぼる。その仕事は「最も退屈な仕事」なのではなく、世界を編集するうえでの「最も勇気のある仕事」だった。
──千夜千冊6夜『辞書の世界史』
気胸の要因となるのは気腫性嚢胞、通称ブラである。ブラといえば、ブラジャーだなと安易な連想に導かれるままJapanKnowledgeで調べたら、気腫性嚢胞はbullaで、ブラジャーはbraであった。全く無関係だったか。そりゃそうか。
『数え方辞典』にまでブラジャーが載っていることに驚く。メーカーが製品の立体性を強調するために「枚」よりも「個」と数えるとあった。なるほどなぁ。職人のこだわりは数え方にもおよぶのだと納得。
それにしてもブラジャーはなぜことごとく男性名詞なのだろうか。意味深だ。
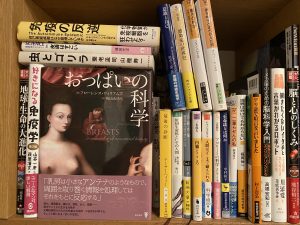
12月4日(金)
◆
ぼくも編集学校では、諸君は諸君なりに工夫したノーテーションやドローイングをしてみるといいよと訴えてきた。何が図示・図解できるかを知ることは、自分に何がわかっていないかに触知できることなのだ。
──千夜千冊1540夜『想像力を触発する教育』
脳と皮膚は、同じ外胚葉由来である。皮膚は身体全体を覆うこととなった第二の脳である。図解は、皮膚で考える訓練である。
昼、吉祥寺で「油そば」をかき込んでから、ゴートクジでMEdit LaboのMTG。あっという間の3時間である。一気にエントロピー増大に向かうMTGのため、半分以上は雑談となる。でもその雑談にふんだんにまぎれる誤った仮説の数々が創発の種に。教材のアイキャッチ画像やワークブックのデザインはやはり吉村さん案で、触知的なものに向かう。これまたイミシン。
12月5日(土)
◆
ワインバーグが考えていた「システム」とはいったいどういうものということだが、一番大事なことは、第1には、システムには「境界」があるということ、第2には、そこにはそのシステムを見る「見方」が含まれているということだ。
──千夜千冊1230夜『一般システム思考入門』
病理診断、[守]伝習座のオブザーブ、MEdit Labo用のデザイン描画の三位一体で構成された一日。
システム的、構造的なQを設定してアナロジーを解説していた中村麻人師範、自ら掘り起こした具体例をもとに新たな意味を創発する方法を解いた武田英裕師範、そして、英語の語源解説からふたりの講義をまとめた渡辺恒久師範の用法講義、それぞれどれも見事だった。
幾重ものIN-OUTでわたしというシステムができる。見方と境界設定の仕方によって、隠されたたくさんのわたしもたくさんのあの人もたくさんの企画も見えてくる。既知の中に未知を見出す余地を。
【をぐら離】
小倉加奈子
編集的先達:ブライアン・グリーン。病理医で、妻で、二児の母で、天然”じゅんちゃん”の娘、そしてイシス編集学校「析匠」。仕事も生活もイシスもすべて重ねて超加速する編集アスリート。『おしゃべり病理医』シリーズ本の執筆から経産省STEAMライブラリー教材「おしゃべり病理医のMEdit Lab」開発し、順天堂大学内に「MEdit Lab 順天堂大学STEAM教育研究会」http://meditlab.jpを発足。野望は、編集工学パンデミック。
「御意写さん」。松岡校長からいただい書だ。仕事部屋に飾っている。病理診断の本質が凝縮されたような書で、診断に悩み、ふと顕微鏡から目を離した私に「おいしゃさん、細胞の形の意味をもっと問いなさい」と語りかけてくれている。 […]
苗代主義と医学教育◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子
医学知識が2倍になるまでにかかる日数を調査した研究がある。1950年頃は、50年かかっていた試算が、私が医学部を卒業した2002年ころには5年、そして2020年の段階ではどうなっていたか。──なんと、73日である。 &n […]
漢方医学という方法◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子
干支は、基本的に中国やアジアの漢字文化圏において、年・月・日・時や方位、さらにはことがらの順序をあらわし、陰陽五行説などと結合してさまざまな占いや呪術にも応用される。東洋医学の中でも「中医学」は、主にその陰陽五行説を基盤 […]
クリスマスを堪能するドクターたち◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子
◆メス納め?ガス納め? 365日、年中無休の医療機関。クリスマスも正月もない、というイメージをお持ちの方が少なくないと思うのですが、年末の院内行事はかなり華やかです。コロナ禍ではさすがにそんな余裕はありませ […]
現在、MEdit Labでは、高校生たちに医学をテーマにしたボードゲームづくりを体験してもらっている。私が書いたコラムに「いいね!」してくれた、ただそれだけを伝手に、強引にもお近づきになった山本貴光さんが、ずっとこのワー […]






コメント
1~3件/3件
2025-07-15

草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。
「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。
2025-07-13

『野望の王国』原作:雁屋哲、作画:由起賢二
セカイ系が猖獗を極める以前、世界征服とはこういうものだった!
目標は自らが世界最高の権力者となり、理想の王国を築くこと。ただそれだけ。あとはただひたすら死闘に次ぐ死闘!そして足掛け六年、全28巻費やして達成したのは、ようやく一地方都市の制圧だけだった。世界征服までの道のりはあまりにも長い!
2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。
配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。
昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。