タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。




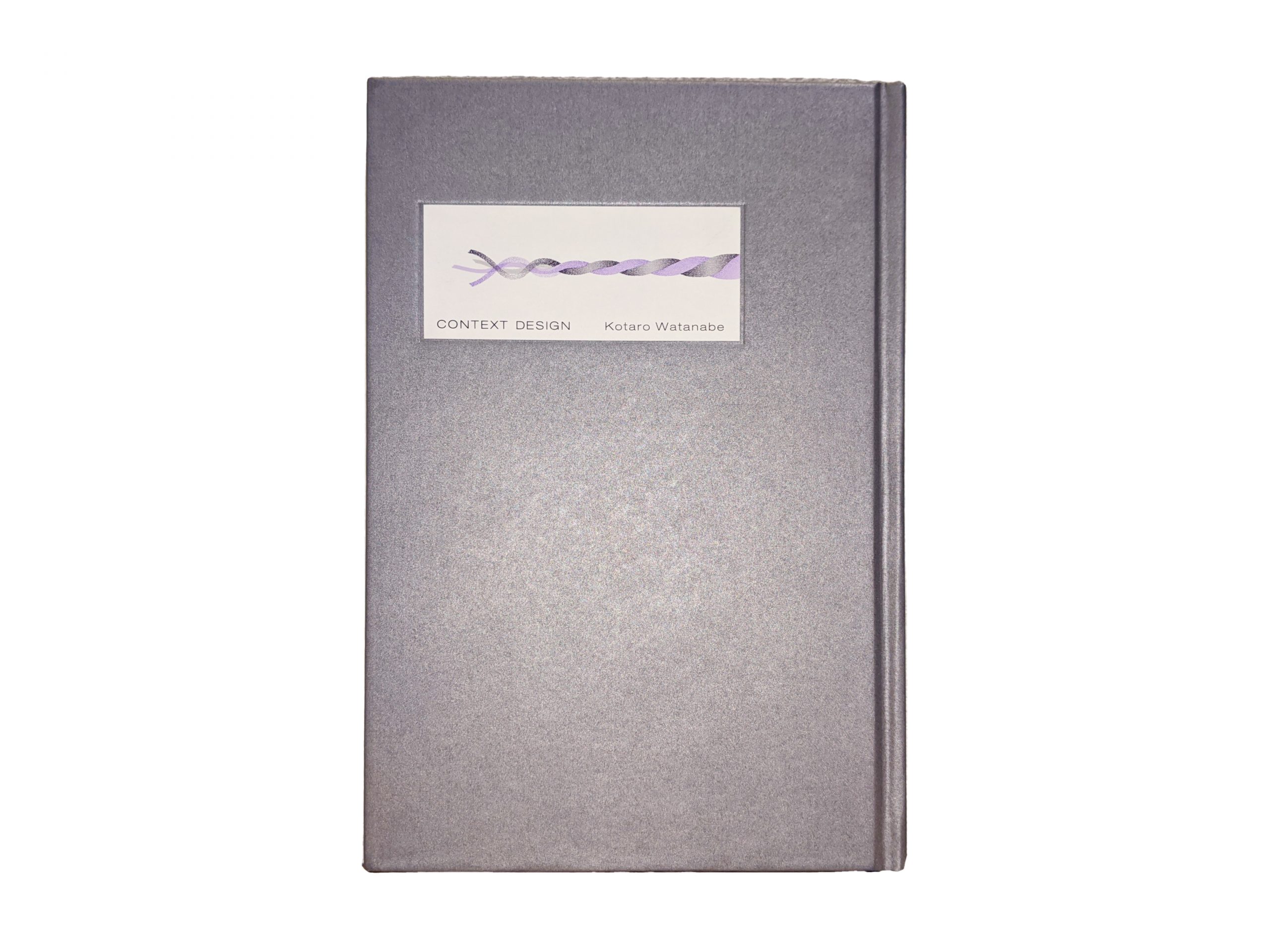
「どこにもない学校」の20年を振り返る「多読ほんほんリレー」も、ついに2019年までバトンが渡ってきました。2020年9月のいま、多読ジム【書院】というトラックに佇むみなさまの背中をめがけて、ひと巡りの季節を走ります。
2019年。総括するにはいささか近すぎるような、それでいて、もはや遠くのこととも思える、コロナ前の世界がそこにありました。
春の出来事として記憶に鮮やかなのは、やはり新元号「令和」の発表と天皇陛下の皇位継承でしょうか。松岡校長は『万葉集の詩性 令和時代の心を読む』に、転(うたた)して継承されていく歌(うた)についての文章をよせられています。また、5月に創刊された言論誌『ひらく』の第一号巻頭対談「日本文化の根源へ」も見逃せません。
夏、海外に目を向けると、香港での大規模デモ、トランプ大統領の北朝鮮訪問、ブレグジット強硬派のジョンソン首相の就任、米中貿易摩擦など、影響の大きさを測りかねる、さまざまな政治経済のうねりがありました。国内では「来年の今頃」に控えた東京五輪・パラリンピックについて、覆りようのない予定としての想像を、誰もが持っていたことと思います。
秋には台風15号・19号をはじめとする天災が続きます。国連気候行動サミットでのグレタ・トゥンベリさんの訴えも話題を呼びました。より生活に密着した事件といえば、消費税の増税。景気の冷え込みが心配されていましたが、まさかコロナ・パンデミックで追い打ちがかかるなどとは、誰も予想していませんでした。
そして冬。多読ジム season 01の募集が始まったのがこの頃です。本楼の高い位置に掲げられた【工冊會】の書、「工」が「互」とも見えた楽しげな文字の形を、印象深く覚えています。私個人としては、自分の入門期(37守, 2016年)の感門校長校話「伝承と継承」のデータをお預かりして、わずかばかり編集を加え、遊刊エディストに公開できたことが大切な思い出となりました。
さて、この2019年を語るにふさわしい一冊は何か。
同年に刊行・翻訳された本の中では、國分功一郎・互盛央『いつもそばには本があった。』、モリー・バング『絵には何が描かれているのか』の二冊がまず候補に挙がりました。それぞれ『本から本へ』『デザイン知』とも重ねてみたい。1694夜『トポフィリア』から1729夜『牡猫ムルの人生観』に至る36冊もめくるめく陣容です。
悩んだ末に、大好きな1715夜『リヒテンベルクの雑記帳』から連想の糸をたぐり、こちらの一冊を本棚から引き出しました。刊行は、2019年10月21日。
世に放たれた弱い文脈は知らず識らずのうちにリレーされる。(…)それは微かなノイズだったのかもしれない。しかしそのノイズにこそ望みをかけたいのだ。その端緒にこそなにかが潜んでいる。
加藤めぐみ
編集的先達:山本貴光。品詞を擬人化した物語でAT大賞、予想通りにぶっちぎり典離。編纂と編集、データとカプタ、ロジカルとアナロジーを自在に綾なすリテラル・アーチスト。イシスが次の世に贈る「21世紀の女」、それがカトメグだ。
「こういうことなんじゃないか」という感触をもって着地した方が、3シーズン中で最も多かったように感じる。 Hyper-Editing Platform[AIDA]の3期目を締めくくる最終講が、3 […]
巷では、ChatGPTが話題である。 ChatGPTは、人工知能研究所のOpenAIが2022年11月に公開したチャットボットで、インターネット上のデータを学習し、幅広い分野の質問に対して回答 […]
其処彼処に「間」が立ち現れる AIDA Season3 第4講
徴、脇、綾、渝、寓、異、擬、縁、代、⾔、格、和、龢、道、空、境、異、感、狂、語、拡、化、仄、情、端…。 AIDA Season3 第4講に、座衆たちはそれぞれの「しるし」の一字を携えて臨んだ。「日本語と […]
聖なる顕現は必ず「しるし」をもっていた AIDA Season3 第3講後半
大阪の空は快晴。「日本語としるしのAIDA」第3講・特別合宿の「嵐」は、一夜明けてますます勢力を強めた。 安藤礼二氏の案内つきという、たいそう贅沢な四天王寺見学を堪能したのち、一行は近畿大 […]
むべ山風、台風と革命が渦巻く AIDA Season3 第3講前半
「大変ですよここは。嵐になると思います」。 松岡座長のニヤリと不敵な予言とともに、AIDA Season3 第3講が幕を開けた。一泊二日の合宿仕立てで行われる第3講の現場は、近畿大学・アカデ […]




コメント
1~3件/3件
2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。
2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥
LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。
2026-01-20

蛹の胸部にせっかくしつらえられた翅の「抜き型」を邪険にして、リボンのような小さな翅で生まれてくるクロスジフユエダシャクのメス。飛べない翅の内側には、きっと、思いもよらない「無用の用」が伏せられている。