私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。




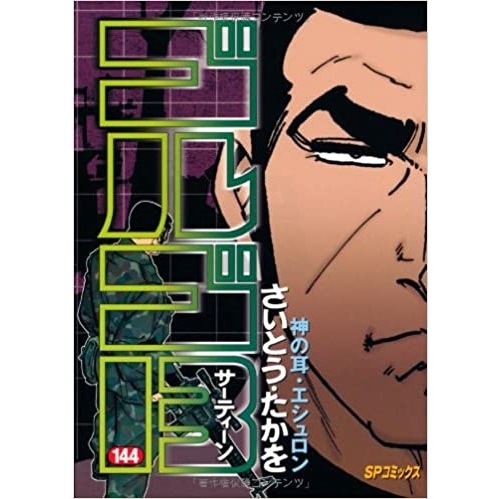
さる九月、劇画家さいとう・たかを氏の訃報が報じられました。
近大DONDENのLEGEND50は、戦後マンガを代表するレジェンドだけに、平均年齢も高く、物故者も少なくないのですが、当コラム連載中に訃報を聞くことになったのは初めてです(*)。
(*)本記事脱稿(10/24)後、間もなくして、白土三平氏の訃報が報じられました。ご冥福をお祈りいたします。これでLEGEND50の物故者は15人になりました。(10/28追記)
というわけで今回は急遽、さいとう・たかを先生を取り上げることにしました。
巨星墜つ…と、いうことで、さいとう・たかをの訃報は各界に波紋を呼びましたが、そもそも、さいとう・たかをという人は、この業界では永らく不遇な扱いを受けてきた人です。
『ゴルゴ13』で圧倒的な人気を誇りつつも、批評家の間では、ほとんど相手にされてきませんでした。
『ゴルゴ13』って、どちらかというと、コアなマンガファンというより、暇つぶしでマンガを読んでる人に好まれてるようなイメージがありますよね。
たとえば「ミステリ好きです」っていう人に、どんなの読んでるんですか?と聞いてみて「西村京太郎とかですかね」と言われたら、どう思います?「へええ・・・(苦笑)」っていうリアクションになりませんか。
さいとう・たかをにも、それと似た感じがあります。元首相・麻生太郎氏のように、マンガ好きを公言していながら、好きなマンガの筆頭に『ゴルゴ13』を上げただけで、もう足下を見られるのは必定。「ああ、ハイハイ。好きと言ってもそのレベルね」と値踏みされてしまいます。
しかし、たとえ、さいとう・たかをの読者層がどんなものであれ、さいとう・たかを自身を馬鹿にしてはなりません(西村京太郎もです)。
俗に「職人」/「芸術家」という分け方がありますが<1>、さいとう・たかをは、芸術家でも職人でもなく、いわば大衆食堂の親父さんのようなスタンスなんですね。「ごちゃごちゃした能書きはいい。とにかく旨いもんを食わす。」これです。
そして、さいとう・たかをは大衆食堂の親父さんは親父さんでも、ただの親父さんではありませんでした。全く新しいタイプの大衆食堂を考案した真の革命者だったのです。
■「劇画」=さいとう・たかを
さて、さいとう・たかをと言えば、なんといっても「劇画」の代名詞です。
くしくも前回とりあげた大友克洋に代表される「ニューウェーブ」こそが、まさに劇画的なるものを一掃する一大ムーヴメントでもあったわけですが、そのことの意味を理解するためにも、まずは「劇画」とは何だったのか、ということを知っておく必要があります。
かつて当連載で辰巳ヨシヒロを取り上げた際、「劇画の本家本元」という紹介をしましたが、それを読んだとき「これのどこが劇画?」と思った人も多いのではないでしょうか。
たしかに辰巳ヨシヒロは「劇画」の命名者ではありますが、彼の絵は世間一般が思う「劇画」とはちょっと違います。
ではどんな絵を「劇画」と言うのか?と聞かれたら、十人中、九人までが、さいとう・たかをの絵を思い浮かべるんじゃないでしょうか。メリハリのあるGペンのタッチに、マジックインキのぶっとい線が混ざり、あの独特の筆圧の強いスピード感のある絵。これこそ劇画の中の劇画ですね。
さて、今回の模写は、やはりこの作品。
さいとう・たかをには、たくさんの作品があるのですが、やはりこれを選ばないと収まりが悪いでしょう。
さいとう・たかを「ゴルゴ13」模写
(出典:さいとう・たかを『ゴルゴ13』157巻リイド社)
毎度おなじみ、ゴルゴの狙撃シーンにしてみました。
スコープを覗くゴルゴのカットと、狙撃のカットが、【一ページ内に収まっているシーン】を探してみたのですが、意外と見つからなかったので(202巻全部探したらあるのかもしれませんが…)、今回はちょっとオマケして一ページ半にしてみました。最後の三コマは次のページになります。
至近距離から人質にピッタリ銃口を向けた二人の男。狙撃の訓練を受けた、この両者を瞬時に排除しないかぎり人質の命はない、という困難なミッションに挑むゴルゴというシーンです。
スコープのカット→ゴルゴのアップ→二人の目撃者のアップ→標的にズーム→ゴルゴの目のアップ→狙撃→ヒット、という流れが、きわめてスムーズな【カットバック】で表現されています。最後のカットでは、コマとコマの間を吹き出しで繋ぎ、さらに描き文字でその下のコマに繋ぐことで、出来事が瞬時に起こったことを表現しています。
それにしても、模写してみて再認識したのは、やはりゴルゴの目は濃い!!
ここまでやるかっていう感じで、描いてて楽しかったですね。上まぶたはアイシャドーのようにこってりと太く、その上にさらに細い線を引いて二重瞼にしています。目尻のまつ毛もかなり長く反り返っており、その下にもまつ毛がくっきりついていて、かなりバチバチな目ですね。目の細さとのギャップで異様な印象を醸し出しています。眉毛は毛筆のイメージで、とめはねをはっきり出すのがポイントですね
そして、最後のキメとなる弾着のカット。眉間の黒ポツがお決まりのパターンです。マジックで、わりと荒っぽく処理していますね。
ペンや筆に含ませたインクを、フッと息で飛ばして血しぶきを表現する「吹きつけ」と呼ばれる手法があります。劇画系が好んでこれを使っていたのですが、さいとう先生は、意外と使わないのですね。昭和30年代頃まで、マンガの中で血しぶきを描くなんてことは常識ハズレの所業だったのですが、そうした常識をぶち破ったのが、さいとう・たかをや白土三平ら貸本劇画の人たちでした。
彼らは【マジックインキ】による血の表現、というのを始め、これが手塚治虫の『新選組』などにも影響するのですが<2>、その後、「吹きつけ」が流行り始めると、マジックインキの技は廃れていきました。ところが、さいとう・たかをだけは、ずっとマジックインキを使い続けているのですね。太い輪郭と滲んだ感じがお好みなのでしょうか。
ところで、さいとう・たかをを模写するなら、やっぱりGペンだろうと思って、そうしたのですが、ゴルゴの顔など、ちょっとタッチがつきすぎちゃいました。NHKの「漫勉」などを見た限りでは、後年のさいとう先生は、あまりGペンを使っていなかったようです。そう思って、あらためて見てみるとゴルゴの顔ってミリペンぽいんですよね。かなり以前の作品でもそうです。いつからなんでしょう。浦沢先生も、ちょっと驚きながら「いつからなんですか?」と聞いていましたが、なんだかはっきりしませんでした。
さいとう・たかをといえば、マンガの作画にGペンを持ち込んだ革命者、「マスター・オブGペン」みたいな人なのに、なんてことだ…とも思いましたが、よく考えると、Gペンをミリペンに持ち替えたことが、案外ゴルゴが命脈を保った理由の一つだったのかもしれません。
私の描いた二コマ目のGペンゴルゴなど、やっぱりちょっと時代がかっていますよね。だいたい70年代に劇画タッチで一世を風靡した作家たちは、ほとんど絶滅してしまい、ただ一人の生き残りが、さいとう・たかをでした。
そのことの意味を考えると、自分の持ち味であったGペンを、あっさり捨て去ってしまえるドライさにこそ、さいとう・たかをの本質が隠されているようにも思うのです。
■ジャイアンの悲哀
さいとう・たかをはマンガ家の中でも、かなり特異なキャラの持ち主です。
先日、朝日新聞に寄せられたさいとう・たかをの追悼記事の中で、夏目房之介は、「漫画家にはいじめられっ子が多いが、彼はむしろ完全にジャイアン・タイプで、若い頃は相当ヤンチャだったらしい」と書いていました。
たしかに、さいとう・たかをは、中学生の頃から、多くの子分を引き連れてのし歩くようなガキ大将であったらしく、貸本劇画仲間のあいだでも、ちょっと浮いた感じの人でした<3>。
だいたい貸本系の人たちって、みんな飢え死にするんじゃないかってぐらい貧乏な人たちばかりなんですが、さいとう先生だけは、ついぞそんなことはなかったそうです。ギャラもほかの人より、かなり良かったらしい。とにかく腕が良く、作品は圧倒的な人気があったので、どこも喉から手が出るほど原稿を欲しがったのですね。
もっとも同業者からのやっかみもかなりあったようです。純朴青年の多いマンガ家仲間の中では珍しく強面タイプな上に、あけすけにビジネスライクな創作哲学をぶち上げるので、煙たがる人も多かった。
永島慎二の『漫画家残酷物語』シリーズでは、明らかにさいとうをモデルにしたと思しきキャラが現れ、ガサツな言動で主人公を引き立てます。辰巳ヨシヒロ『劇画漂流』に出てくるさいとう・たかをも、理想のないドライな男として登場し、情緒に欠ける大雑把な言動で辰巳たちを呆れさせます。
(永島慎二『漫画家残酷物語』①ジャイブ/辰巳ヨシヒロ『劇画漂流』下・青林工藝社)
当時の劇画仲間に、さいとう氏の印象を聞くと、だいたい似たようなもので、仲間内でも「どうもアイツはいかがなものか」という空気があったようです。
しかし、さいとう氏自身にインタビューしたものを見ると、案外、彼にはナイーブな一面もあって、外見の印象とは異なり、自分の考えや、やり方が仲間たちに全然理解されないことに、そうとう煩悶していたらしいこともうかがわれます。
さいとうは、貸本業界のトップランナーでありながら、どうも他の劇画工房の仲間たちとはソリが合わず、何かと食い違うことが多かったようですね。
■この世界、ガラ空きやんけ!
さいとう・たかをは、自分はマンガを描くのが好きでこの世界に入ったのではない、マンガ家が将来絶対伸びる職業だと確信したからだ、と言い切ります。この表現には、幾分誇張があるかとは思いますが、さいとうが“産業としてのマンガ”ということを真剣に考えていた当時唯一の人物であったことは間違いないでしょう。マンガが今日のような巨大産業になることなど、その頃の感覚では夢のまた夢でした。
そして、貸本業界に入ってみると、同業者も出版人も誰一人マンガを産業として捉えていない事実に気づいたさいとう青年は、こう思ったそうです。
「この世界、ガラ空きやんけ!」
さいとうの目には、同世代の貸本劇画仲間は、みんな世間知らずのお坊ちゃんに見えた。フワフワした理想を語るばかりで、誰も職業としてのマンガ家ということを真剣に考えていない。さいとうは、個人の才能は限られているので、より理想的な制作方法は分業制に違いない、という持論を、ことあるごとに披露していたそうですが、他の仲間たちは鼻で笑うだけで相手にしませんでした。
辰巳ヨシヒロや松本正彦のような純粋マンガ青年の目からは、「またジャイアンが、雑な理論で妄想的なことを言ってる」と見えたのでしょう。
しかし、さいとうは真剣でした。
様々な試行錯誤の果てに、さいとうは自らの理論を実践していくことになります。そして、さいとうの考案した、この集団制作システムは、程度の差こそあれ、のちに多くのマンガ家の採用するところとなりました。特に60年代以降、週刊連載がマンガの主流となると、もやは個人の力ではマンガ制作は不可能となり、誰もが分業でマンガを描くようになります。
しかし、さいとうがこのプランを構想していた昭和30年代の段階では、それはまだ気宇壮大なホラ話にしか聞こえませんでした。
1959年、関西在住の八人の仲間たちで結成された「劇画工房」は、まさに歴史が動いた転換点でしたが、この「工房」を単なる親睦団体ではなく、本格的制作集団として捉えていたのは、さいとうただ一人でした。のちに「さいとう・プロダクション」として結実する本格的分業システムは、当初、劇画工房の中で行おうと、さいとうは画策していたようです。
しかし、さすがにそれは上手くいきませんでした。さいとうは、神戸大学の経営学科を卒業し製薬会社に勤めていた親族一の秀才である実兄・斉藤發司を口説き落として、東京に呼び寄せます。劇画工房の本格的経営に参画させるためでした。しかし、辰巳・松本ら主要メンバーと、さいとうとの間にある温度差に驚いた兄は「いったいどういう話になってるんだ」と激怒したとか。
結局、「劇画工房」は一年余りで空中分解。それから間もなくの1960年4月、「さいとう・プロダクション」が誕生します。さいとう・プロは、兄・發司が経営部門を一手に担うことによって、不安な処女航海を乗り切ることになりました。そして、これが、のちのち大成功を収めていくことになるのです。
■新ジャンルの創造
マンガ業界の未来を誰よりも正確に予測し、最適なシステムまでも独自に考案した、さいとう・たかをの冷徹な知性には驚かされるばかりです。しかし当時は誰もそれに耳を貸しませんでした。
「なんで、こんなに理路整然と説明しているのに、誰もわかってくれへんのや」と、さいとうは首をかしげるばかりだったそうです。
なんといっても風貌もキャラクターもジャイアンそのものであるさいとう・たかをのことを、みんなちょっぴりナメていたんじゃないでしょうか。「またジャイアン・リサイタルをするとか言ってるよ。困ったなあ」と、お互い顔を見合わせていたのでしょう。
しかし、さいとうの冷徹な知性は、分業システムの構想にとどまるものではありませんでした。マンガという表現ジャンルそのものの可能性をも見据えていたのです。
60年代末頃から大学生がマンガを読む、ということがジャーナリズムを騒がせるようになったことは、白土三平の回のときに書いた通りですが、それ以前の常識は、マンガは、せいぜい小学校高学年ぐらいで卒業するものでした。
しかし、さいとうは、今マンガを読んでいる小学生たちが、中学生、高校生になっても読みたくなるようなマンガを創ることができれば、そこには広大な沃野が広がっていることになる、と考えたのです。そして、貸本劇画を描くかたわら、あちこちの大手出版社に話を持ち込み、持論をぶち上げたと言います。
しかし当然のことながら、さいとうの、このアイディアは、誰も相手にはしませんでした。「ワシに50ページよこせ。そしたら大人向けの大河マンガを描いたる」というのですが、そんなジャンルのマンガは、その当時、実在しないのですから、暴論としか思えません。
園山俊二の回のときにお話ししたように、当時、大人の読むマンガというのは、一コマとか四コマとかのカトゥーン漫画のことで、小島功の4ページ漫画が「長編」などと呼ばれていた時代です。手塚系の少年マンガの延長にある「青年マンガ」の系譜は、貸本劇画の中で、その萌芽が胎動していたとはいえ、まだ、はっきりと形あるものとはなっていませんでした。それを「50ページの大河マンガ」とか言われても正気の沙汰とは思われません。
しかし、さいとうの迫力に押し切られてしまった出版社が、ただ一社ありました。大人マンガの専門誌「週刊漫画TIMES」を刊行していた芳文社です。「50ページはなんぼなんでもムチャですが、とりあえず20ページぐらいでどうでしょう」ということで本誌別冊の方に、さいとうの青年マンガが掲載されたのです。
その結果は出版社も驚くようなバカ受けでした。すさまじい反響を受け、芳文社は、次々と、さいとう・たかを作品を雑誌に掲載し始めます。この「青年向けマンガ」という新しいスタイルは、何かとてつもないポテンシャルがあるらしいと出版人が気がつくのは時間の問題でした。
(『さいとう・たかをゴリラコレクション劇画1964』リイド社)
芳文社時代の短編をセレクトしたアンソロジー。
最も瑞々しく躍動していた頃のさいとう作品が味わえる絶必の一品。
大判サイズなのもうれしい。
さいとう・たかをで確信を得た芳文社は、1966年、本邦初の青年マンガ誌「コミックmagazine」を創刊します。そして、それを見た他社も一斉に動き始めました。翌67年には双葉社より「週刊漫画アクション」、少年画報社より「ヤングコミック」が創刊、68年には日本文芸社「漫画ゴラク」、小学館より「ビッグコミック」、秋田書店より「プレイコミック」が創刊されます。
それはまさに一瞬の出来事でした。
さいとうの始めた青年向けマンガ、すなわち「劇画」が、あれよあれよという間に市場を制覇してしまったのです。そればかりか少年誌の「劇画化」も急速に進行。内田勝編集長体制による「少年マガジン」黄金期の到来です。
いつしか「劇画」は、ほとんど「ストーリーマンガ」と同義になるほど浸透していきました。まさに圧勝です。ジャイアンの大言壮語は、すべて正しかったことが証明されたのです。
しかし、ホントにそうでしょうか。
さいとう・たかをは、ただ一つ思い通りにならなかったことがあると言います。「さいとう・プロダクション」はさいとう・たかをという個人名を脱して自己増殖を繰り広げていく、そういう将来を彼は構想していたらしいのです。
しかし、事はそのようには進みませんでした。その原因を、さいとうは、自分がなまじ絵が描け、話を創れることにあったと言います。もしも自分がプロデューサーに徹することができていれば、より大きな成功を掴めていたはずだと…。
しかし、そこはちょっと怪しいでしょう。
さいとうがプロダクションの構想を描いてから半世紀以上、たしかにマンガ制作は高度化し、分業化も進みました。しかし固有名が完全に消え去ることはなかったのです。
結局「さいとう・プロ」の大成功をもたらしたのは、さいとう・たかをという類まれなる個人だったのです。
どうやら、さいとう・たかをは自分の才能を過小評価していたようです。
◆◇◆さいとう・たかをのhoriスコア◆◇◆
【一ページ内に収まっているシーン】56hori
こういったシーンがあまりなかったのは、ある程度、意図的なのかもしれません。さいとうの自伝記『俺の後ろに立つな』(p50)によるとページめくりの効果の例として、最後のコマで狙撃シーン、次のページで狙撃の結果を見せる、といったやり方を紹介しています。
【カットバック】68hori
ゴルゴ、標的、観察者、三者三様の在りようをスムーズに見せるのにベストな並べ方です。
【マジックインキ】72hori
描き文字もそうですね。さいとう・たかをの描き文字は、もう100%マジックインキの一点張り。これは初期の頃から一貫しています。独特の味わいのあるマジックの線で、的確な場所に入れています。
<1>「職人」/「芸術家」
戦後「夜の会」を発足させた花田清輝や岡本太郎らアヴァンギャルド芸術運動の推進者たちは「アルチザン(職人)になるな。アルチスト(芸術家)たれ」を標語にしていました。かつて「職人」という言葉には、どこかマイナスイメージがあったのです。それが徐々に、カッコいい響きを持ったプラスイメージに変わっていったのは1970年代以降のことだと言います。
<2>手塚治虫への影響
どんなに「巨匠」になっても、常に新人に嫉妬し、タメで張り合おうとし続けていた手塚治虫は、新しいトレンドや手法が出てくると、すぐに反応して、大人げないぐらいに罵倒したりするのですが、それでいて、すぐにそれを自作に取り込むようなところがありました。『新選組』の血しぶき表現は、まだどこか、おっかなびっくりなところがありますが、やがて自家薬籠中のものとしていき、70年代にはいると盛大に血しぶきを飛ばしまくります。手塚マンガに出てくる「吹きつけ」の血しぶきは、なかなかみごとなものです。よく出てくるので皆さんも探してみてください。
<3>ガキ大将タイプ
若き日のさいとう・たかをが、仲間たちと道を歩いていて、ヤクザに因縁をつけられた時のエピソードが残っています。その時、現場にいた石川フミヤスが、のちに証言しているのですが、さいとうは仲間たちをおいて、ヤクザと二人で道の向こうに消えていったとか。物陰からこっそり石川氏が窺ってみたところ、くだんのヤクザは、眼光鋭いさいとうの迫力に恐れをなし、「どうも、すみませんでした」と頭を下げていたというのです。さいとうは近隣のヤクザからも「先生、お散歩ですか」と挨拶されるほどだったとか。本職のヤクザさんの動物的カンが、この人のカンロクはホンモノと認めざるを得なかったのですね。
アイキャッチ画像:さいとう・たかを『ゴルゴ13』144巻・リイド社
堀江純一
編集的先達:永井均。十離で典離を受賞。近大DONDENでは、徹底した網羅力を活かし、Legendトピアを担当した。かつてマンガ家を目指していたこともある経歴の持主。画力を活かした輪読座の図象では周囲を瞠目させている。
山田風太郎『人間臨終図巻』をふと手に取ってみる。 「八十歳で死んだ人々」のところを覗いてみると、釈迦、プラトン、世阿弥にカント・・・と、なかなかに強力なラインナップである。 ついに、この並びの末尾にあの人が列聖される […]
文章が書けなかった私◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:堀江純一
デジタルネイティブの対義語をネットで検索してみると、「デジタルイミグラント」とか言うらしい。なるほど現地人(ネイティブ)に対する、移民(イミグラント)というわけか。 私は、学生時代から就職してしばらくするまで、ネット […]
桜――あまりにもベタな美しさ◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:堀江純一
今回のお題は「桜」である。 そこで、まず考えたのは、例によって「マンガに出てくる桜って、なんかなかったっけ」だった。(毎回、ネタには苦労しているのだ) しかし、真っ先に浮かんでくるのは、マンガよりも、むしろ映画やア […]
【追悼】鳥山明先生「マンガのスコア」増補版・画力スカウター無限大!
突然の訃報に驚きを禁じ得ません。 この方がマンガ界に及ぼした影響の大きさについては、どれだけ強調してもしすぎることはないでしょう。 七十年代末に突如として、これまでの日本マンガには全く見られなかった超絶的な画力とセンスで […]
今月のお題は「彼岸」である。 うっ…「彼岸」なのか…。 ハッキリ言って苦手分野である。そもそも彼岸なんてあるのだろうか。 「死ねば死にきり。自然は水際立っている。」(高村光太郎) という感覚の方が私にはしっくりく […]







コメント
1~3件/3件
2025-07-03

私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。
2025-07-02

連想をひろげて、こちらのキャビアはどうだろう?その名も『フィンガーライム』という柑橘。別名『キャ
ビアライム』ともいう。詰まっているのは見立てだけじゃない。キャビアのようなさじょう(果肉のつぶつぶ)もだ。外皮を指でぐっと押すと、にょろにょろと面白いように出てくる。
山椒と見紛うほどの芳香に驚く。スパークリングに浮かべると、まるで宇宙に散った綺羅星のよう。
2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。
写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。