発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。
写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。




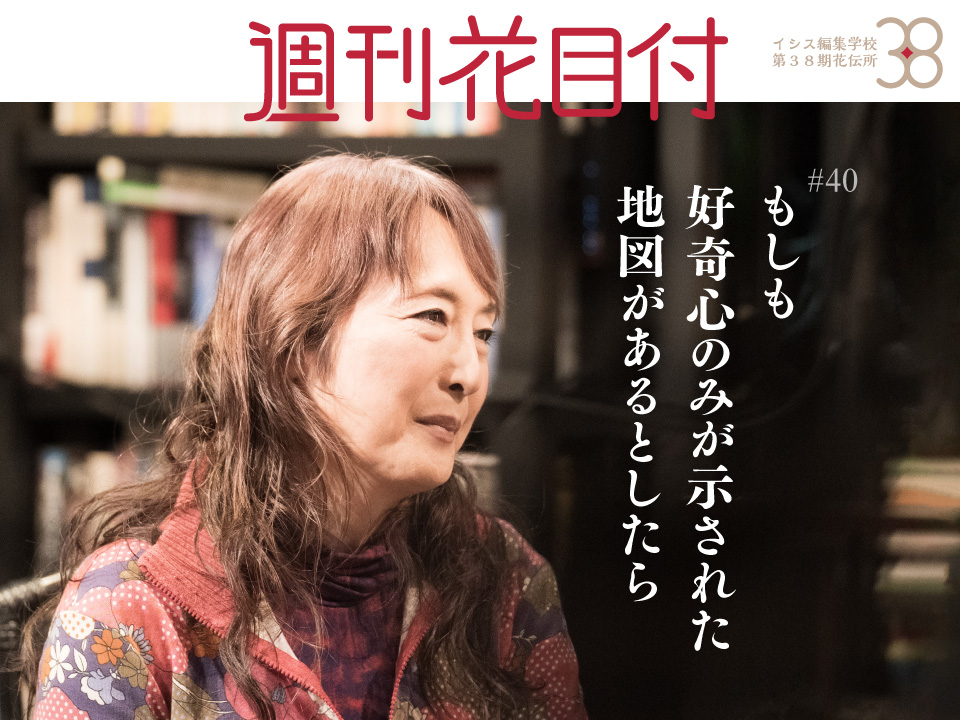
■2022.10.31(月)
内海太陽錬成師範が、花林頭(カリントウ)の先鋒に立って花Q林の開宴を告げた。放たれた公案は「面影」を巡る問答だ。方法日本を地に置きながら、「3A」「ないものフィルター」「略図的原型」など方法知のプロフィールとイメージメントを炙り出そうとしている。
ところで、内海が「開幕」ではなく「開宴」と呼び掛けたことに関心を示す者はいたが、「宴」のキーワードに反応して入伝式での師範講義を想起する者は見えなかった。
■2022.11.01(火)
道場での式目演習は、基本的に指導がつかない。式目演習は「編集的自己の自立」へ向かう修練だからだ。
だが、このいわば壁打ちのような自学自習に孤独を感じる入伝生は少なくない。自身と向き合って試行錯誤を積み重ねる体験よりも、常に他者からの眼差しと評価に包まれる環境にむしろ居心地の良さを感じているのかも知れない。
加えてパンデミックの影響だろうか、テキストのみでのコミュニケーションが求められる編集稽古のスタイルに今更ながら違和感を言挙げする者も見える。
さて、これら講座カリキュラムの設営意図から零れ落ちる声は、いったい何を表しているのか?
■2022.11.03(木)
「好奇心」と「怖れ」は、同じコインの裏表なのだと思う。
たとえば未知の土地を旅するときに、地図は多くの情報を提供してくれるが、そこには越えるべき山の高さも記されている。地図は冒険を援けもするが、冒険を回避する口実にもなり得るだろう。
そのときロジカルな冒険者ならば、地図が提供する情報を合理的に分析し、心を乱すことなく計画の可否を判断するかも知れない。だが、いずれの選択肢も他方の可能性を完全に否定することはできない筈だ。
一方、アナロジカルな冒険者は、地図がもたらすアフォーダンスによって好奇心を触発されもするし、怖れを増幅させられたりもするだろう。そして、彼/彼女は好奇心と怖れの間でヤジロベエのように揺らぎ続ける。
もしも好奇心のみが示された地図があるとしたら、それは冒険者にどんな体験をもたらすだろう。怖れを含まない好奇心や、好奇心を含まない怖れなどあり得るだろうか?
■2022.11.04(金)
花伝所の指導陣はときおり「花カフェ」と称してザックバランな編集談義を交わす場を設けている。36[花]から始まった習慣で、今期は金曜日ごとの定例開催なので「花金カフェ」と呼ばれている。参加は任意だが、「編集は対話から生まれる」を実践することで情報生成装置として機能することを目論んでいる。
何かを生み出すと言っても、一朝一夕に果実が実ることはない。ここ数期の花伝所を見ていても、蒔いた種が根づくまでには少なくとも4期2年を要する印象だ。2年という時間が長いのか短いのかはさておき、その期間でメンバー構成が4回組み替えられることに注目しておきたい。言い換えれば、4世代をかけてようやく型の継承が行われるということである。これはあくまでも私の主観的な実感値だが、継承の遅延を見込む際には一定の目安になるように思う。
■2022.11.06(日)
「M2:モード」の演習まとめ課題の提出締切日。学衆のエディティング・モデルを受容し、その編集的価値を描出しながら、さらなる編集可能性の拡張を模索する指南を構成する演習だ。
今期、M2で行う指南演習のための題材は、50[守]伝習座での用法解説を受けて「編集思考素」の事例が採用された。ちなみに、35[花]から37[花]までは「いじりみよ」が題材だった。
同じ演習でも題材が変われば体験が異なることは言うまでもない。当然ながら、指導の見どころにも方針にも再編集がかけられている。入伝生にとっては期ごとの演習体験がどう異なるかは較べる由もないが、習得すべき「型」が異なることはない。「型」とは、そこに出入りするものに感応してフィードバックする回路なのである。
アイキャッチ:阿久津健
深谷もと佳
編集的先達:五十嵐郁雄。自作物語で語り部ライブ、ブラonブラウスの魅せブラ・ブラ。レディー・モトカは破天荒な無頼派にみえて情に厚い。編集工学を体現する世界唯一の美容師。クリパルのヨギーニ。
一度だけ校長の髪をカットしたことがある。たしか、校長が喜寿を迎えた翌日の夕刻だった。 それより随分前に、「こんど僕の髪を切ってよ」と、まるで子どもがおねだりするときのような顔で声を掛けられたとき、私はその言葉を社交辞 […]
<<花伝式部抄::第21段 しかるに、あらゆる情報は凸性を帯びていると言えるでしょう。凸に目を凝らすことは、凸なるものが孕む凹に耳を済ますことに他ならず、凹の蠢きを感知することは凸を懐胎するこ […]
<<花伝式部抄::第20段 さて天道の「虚・実」といふは、大なる時は天地の未開と已開にして、小なる時は一念の未生と已生なり。 各務支考『十論為弁抄』より 現代に生きる私たちの感 […]
花伝式部抄::第20段:: たくさんのわたし・かたくななわたし・なめらかなわたし
<<花伝式部抄::第19段 世の中、タヨウセイ、タヨウセイと囃すけれど、たとえば某ファストファッションの多色展開には「売れなくていい色番」が敢えてラインナップされているのだそうです。定番を引き […]
<<花伝式部抄::第18段 実はこの数ヶ月というもの、仕事場の目の前でビルの解体工事が行われています。そこそこの振動や騒音や粉塵が避けようもなく届いてくるのですが、考えようによっては“特等席” […]





コメント
1~3件/3件
2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。
写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。
2025-06-30

エディストの検索窓に「イモムシ」と打ってみたら、サムネイルにイモムシが登場しているこちらの記事に行き当たりました。
家庭菜園の野菜に引き寄せられてやって来る「マレビト」害虫たちとの攻防を、確かな観察眼で描いておられます。
せっかくなので登場しているイモムシたちの素性をご紹介しますと、アイキャッチ画像のサトイモにとまる「夜行列車」はセスジスズメ(スズメガ科)中齢幼虫、「少し枯れたナガイモの葉にそっくり」なのは、きっと、キイロスズメ(同科)の褐色型終齢幼虫です。
添付写真は、文中で目の敵にされているヨトウムシ(種名ヨトウガ(ヤガ科)の幼虫の俗称)ですが、エンドウ、ネギどころか、有毒のクンシラン(キョウチクトウ科)の分厚い葉をもりもり食べていて驚きました。なんと逞しいことでしょう。そして・・・ 何と可愛らしいことでしょう!
イモムシでもゴキブリでもヌスビトハギでもパンにはえた青カビでも何でもいいのですが、ヴィランなものたちのどれかに、一度、スマホレンズを向けてみてください。「この癪に触る生き物をなるべく魅力的に撮ってやろう」と企みながら。すると、不思議なことに、たちまち心の軸が傾き始めて、スキもキライも混沌としてしまいますよ。
エディスト・アーカイブは、未知のお宝が無限に眠る別銀河。ワードさばきひとつでお宝候補をプレゼンしてくれる検索窓は、エディスト界の「どこでもドア」的存在ですね。
2025-06-28

ものづくりにからめて、最近刊行されたマンガ作品を一つご紹介。
山本棗『透鏡の先、きみが笑った』(秋田書店)
この作品の中で語られるのは眼鏡職人と音楽家。ともに制作(ボイエーシス)にかかわる人々だ。制作には技術(テクネ―)が伴う。それは自分との対話であると同時に、外部との対話でもある。
お客様はわがままだ。どんな矢が飛んでくるかわからない。ほんの小さな一言が大きな打撃になることもある。
深く傷ついた人の心を結果的に救ったのは、同じく技術に裏打ちされた信念を持つ者のみが発せられる言葉だった。たとえ分野は違えども、テクネ―に信を置く者だけが通じ合える世界があるのだ。