結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。
配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。
昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。


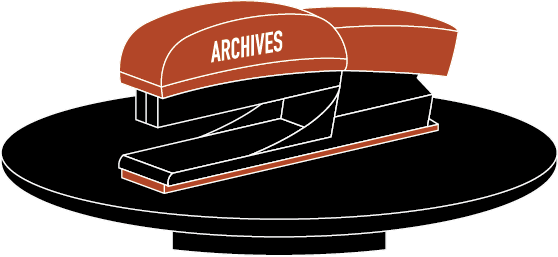

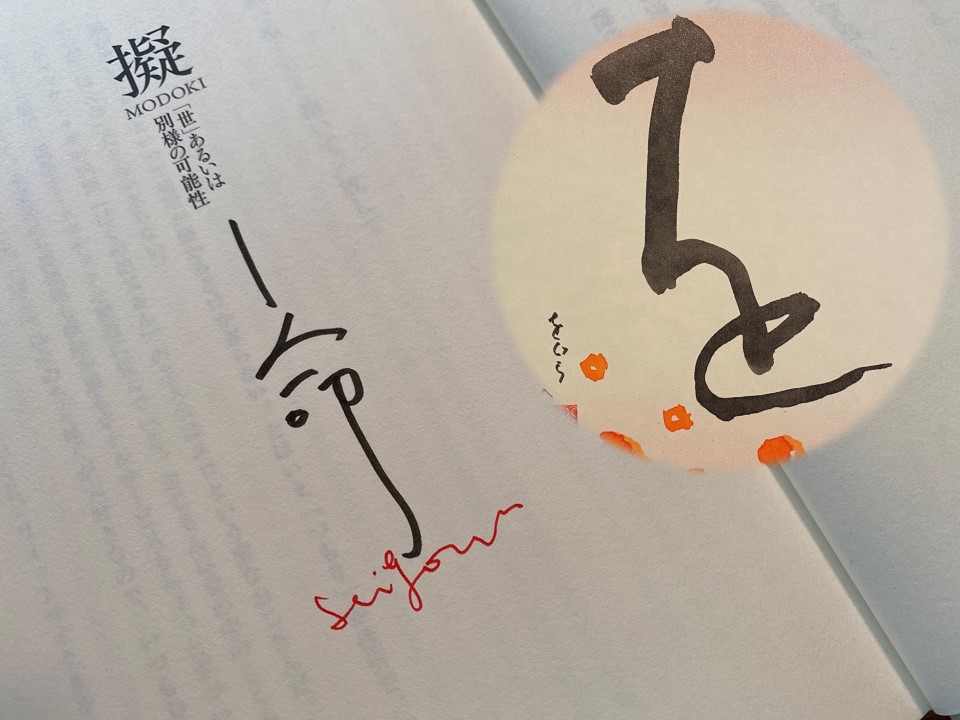
「をぐら離」は、2020年11月に開講した14離を火元組のひとりとして伴走した、析匠、小倉加奈子が、”門外不出”と言われる「世界読書奥義伝[離]」の日常を20週にわたって記したコラムです。松岡正剛火元校長のこれまでの書籍や千夜千冊や発言を紹介するための編集的しかけ、小倉の日常というフィルター越しに離の稽古状況を伝える日記スタイル、離の内外を行き来する縁側的方法を試したコラムの数々。一挙にまとめてみました。
◆14離文巻目次◆
第1週 コスモスとカオス
第2週 情報の世・言葉の代
第3週 境界と構造と関係
第4週 ルールの発見と適用
第5週 メディアとしての書物
第6週 アルス・コンビナトリア
第7週 表象に向かって
第8週 恋愛と戦争と資本主義
第9週 合わせ読み千夜千冊
第10週 見方のサイエンス
第11週 日本という方法
第12週 伝統と革新のあいだ
松岡火元校長は、毎季、すべての文巻に赤を入れ、改訂を繰り返します。絶対に前季のものをそっくりそのまま転用するようなことはしません。ここ数年では、11季に第7週、12季に第10週そして、14季に第9週について、タイトルも出題する稽古内容を含めすべて書き直す大改訂がありました。
◆
いよいよ14離開講の11月へ。心のマスクを外す準備を。萎縮せず逸脱の覚悟を。
14離開講まで1週間。いよいよ入院である。世界読書は視野を固定していてはままならず。つねに東と西、類と個、彼岸と此岸のAIDAでゆれるべし。
◆
正午、14離開講。松岡火元校長から続く開講挨拶リレーは火元組が最も緊張する時間である。指を冷やし痺れさせ、出番を待つ。
をぐら離 文巻第1週 ─「コスモスとカオス」
をぐら離 文巻第2週 ─「情報の世・言葉の代」
をぐら離 文巻第3週 ─「境界と構造と関係」
離学衆の稽古を見守る。刻々とEditCafe上に幾筋もの帯として連なっていく発言の数々は、発芽した自己組織化の跡だろうか。自己、ニューノーマル、恐怖、自粛、陰謀、様々なキーワードが飛び交う。まるでウイルスのようなふるまい。
◆
昼過ぎから別当会議。離学衆の成長ぶりと課題を共有しながら、わたしたち火元組も自身のコーチングの変遷をふりかえる。どうやって、方法への覚醒を離学衆にもたらせるのか。どうやって、離学衆それぞれが持っているはずの才能をわれわれ火元組が表現できるか。言葉の限界が指南の限界。コーチングにもREが不可欠である。
◆
M:
早めに過去を編集した方がいい。つまり当時の意識のままでは思い出に耽らない。ぼくがこの作業に着手したのは十七歳で、いまでは数日前を編集している。<生き方C>
M:
学問より思想。思想より対話。対話より見方。見方はイメージのマネージ。それは図解と用語の組み合わせ。それにはいつも本に書き込みをして文章化へ。<生き方V>
◆
離史上初のオンライン講評会。年末の稽古をもとに火元校長が離学衆ひとりずつに声をかける。編集の奥義が手渡される瞬間を参加者全員で共有する稀有な時間であった。イマジネーションのリプリゼーションに挑戦し続けてきた著者たちと出会い、交際するのが世界読書奥義伝。「すきなひとたちぶんをぼくにする」。憧れの対象で自分を満たすって本当に素敵。会えない人の面影を含めて自分を好きで溢れさせたい。
をぐら離 文巻第5週 ─「メディアとしての書物」
をぐら離 文巻第5.5週 ─「縁起と編集」
をぐら離 文巻第6週 ─「アルス・コンビナトリア」
別当会議。離学衆の来し方・行く末を交し合う。明後日から始まる文巻第7週についても火元組自身が理解をさらに深めるよう校長から促される。転用はアブダクション。資本主義に喰いつくされた世界の表象の断片をかき集める、その盗みと拉致の方法が世界読書奥義伝にある。特に第7週にはつまっている。
◆
をぐら離 文巻第7週 ─「表象に向かって」
をぐら離 文巻第8週 ─「恋愛と戦争と資本主義」
をぐら離 文巻第8.5週 ─「表沙汰に向かって」
表沙汰。連携が素晴らしいテクニカルチームのバックアップの中、初のオンライン開催。両院に分かれての交し合い。離学衆の表情が少しずつ明るくなっていく。田母神方師は壮大なスケールの「おおもと学」、わたしは「表象」そして「擬」についての小さなレクチャーをした。校長の講義は、ワイスの『危険を冒して書く』の千夜からはじまり、上記千夜の引用で終わったが、アイダに尾崎翠や森茉莉の見立て力をお手本にしつつ、読むこと、書くこと、そして理解することの離的な解釈が展開された。校長はこのところ、離学衆に自分の方法を表沙汰しっぱなしである。
離学衆諸君、校長に肖り、校長を擬き、表象に向かいましょう。
◆
誰だって自分を知りたい。自分の「心」を覗きたい。しかし、自己への接近が他者とのあいだの無意識によって介在されているとなると、たんなる思考が自己に近づくなどということは、とうていムリだということになる。むしろ「他者の欲望」に接近することこそが自己に接近する近道だ。ー”心”
「ほんと」と「つもり」はトレード・オフの関係にはあてはまらないものなのだ。それよりも、すべてが「つもり」で出来ているのだと見たほうがうんといい。世界はたいてい「多様の可能性」のほうに向かって開いているのである。このことは、幼い少年と少女以外の誰もがわかっちゃいないことなのである。そう、かれらにとっては「つもり」こそが「ほんと」なのだから。ー”幼”
◆
文字とは、音と線の産物である。そこには音の交通があり、線の交換がある。それを交響曲というにはおおげさであるかもしれないが、なににもまして大胆なコズミック・ダンスであるとはいえるにちがいない。
──遊行の博物学『うたかたの国』p.25
◆をぐら離的考察◆その8
強烈な「ないものねだり」に対する唯一の処方箋は、想像力なのだろう。
◆
14離は閉院しましたが、それぞれの世界読書はスタートしたばかり。退院を寿ぐ5月の退院式では、世界読書のこれからをきっと離学衆それぞれが語ってくれることでしょう。
私も新しい世界読書に向かって離スタートです。
小倉加奈子
編集的先達:ブライアン・グリーン。病理医で、妻で、二児の母で、天然”じゅんちゃん”の娘、そしてイシス編集学校「析匠」。仕事も生活もイシスもすべて重ねて超加速する編集アスリート。『おしゃべり病理医』シリーズ本の執筆から経産省STEAMライブラリー教材「おしゃべり病理医のMEdit Lab」開発し、順天堂大学内に「MEdit Lab 順天堂大学STEAM教育研究会」http://meditlab.jpを発足。野望は、編集工学パンデミック。
「御意写さん」。松岡校長からいただい書だ。仕事部屋に飾っている。病理診断の本質が凝縮されたような書で、診断に悩み、ふと顕微鏡から目を離した私に「おいしゃさん、細胞の形の意味をもっと問いなさい」と語りかけてくれている。 […]
苗代主義と医学教育◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子
医学知識が2倍になるまでにかかる日数を調査した研究がある。1950年頃は、50年かかっていた試算が、私が医学部を卒業した2002年ころには5年、そして2020年の段階ではどうなっていたか。──なんと、73日である。 &n […]
漢方医学という方法◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子
干支は、基本的に中国やアジアの漢字文化圏において、年・月・日・時や方位、さらにはことがらの順序をあらわし、陰陽五行説などと結合してさまざまな占いや呪術にも応用される。東洋医学の中でも「中医学」は、主にその陰陽五行説を基盤 […]
クリスマスを堪能するドクターたち◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子
◆メス納め?ガス納め? 365日、年中無休の医療機関。クリスマスも正月もない、というイメージをお持ちの方が少なくないと思うのですが、年末の院内行事はかなり華やかです。コロナ禍ではさすがにそんな余裕はありませ […]
現在、MEdit Labでは、高校生たちに医学をテーマにしたボードゲームづくりを体験してもらっている。私が書いたコラムに「いいね!」してくれた、ただそれだけを伝手に、強引にもお近づきになった山本貴光さんが、ずっとこのワー […]





コメント
1~3件/3件
2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。
配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。
昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。
2025-07-07

七夕の伝承は、古来中国に伝わる星の伝説に由来しているが、文字や学芸の向上を願う「乞巧奠」にあやかって、筆の見立ての谷中生姜に、物事を成し遂げる寺島ナス。いずれも東京の伝統野菜だが、「継承」の願いも込めて。
2025-07-03

私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。